電気代の高騰は、中小企業の経営を直撃する大きな課題です。この記事では、最新の電気料金事情やコスト削減の具体策、見直しのステップや実際の成功事例、さらに新電力会社の選び方や注意点までを幅広く解説。貴社に最適な電気代削減方法が必ず見つかります。
中小企業の電気代が高騰する背景と現状

電気料金の仕組みと2024年の動向
2024年現在、日本国内の電気料金は「基本料金」と「従量料金」の二本立てとなっており、契約内容や使用量によって毎月の請求額が決まります。電力自由化により選択肢は増えましたが、多くの中小企業は十分な最適化を行っていないケースが目立っています。また、燃料価格の高騰や再生可能エネルギー発電促進賦課金の増加、円安、国際情勢の変化といった複数要因が積み重なり、電気料金は近年大幅に上昇しています。
| 項目 | 主な内容 | 中小企業への影響 |
|---|---|---|
| 燃料調整費 | 石炭・LNG・原油などの価格変動を反映 | 国際相場の上昇により全体的なコスト増 |
| 再エネ賦課金 | 再生可能エネルギー導入促進のための費用 | 毎年上昇傾向、今後も増加見込み |
| 基本料金 | 契約電力(最大需要)に応じて設定 | 過大な契約は無駄なコスト発生につながる |
| 電力自由化 | 新電力会社の参入による選択肢増加 | プラン切替未実施の場合、割高なままのケースも |
2024年以降、政府による一時的な補助金や負担軽減措置が段階的に終了し、電気料金の値上げがさらに進むことが懸念されています。特に、経済産業省の発表や大手電力会社(東京電力、中部電力、関西電力など)の料金改定が頻繁にニュースで取り上げられています。
中小企業が抱える電力コストの課題
中小企業にとって電気代は「固定費」の中でも大きな割合を占める支出です。従業員数や施設規模が大企業に比べて小さいため、大口割引などの恩恵を受けにくく、割高な料金単価が課せられるケースもあります。さらに、経営資源が限られ担当者が兼務となることから、法人契約内容やプラン選択、使用状況の最適化まで手が回っていない企業が多いのが現状です。
また、製造業や飲食業、小規模オフィス、クリニックなど業態ごとに「電気の使い方」は大きく異なるため、業態ごとに最適な契約や運用を選ぶ必要があります。しかし、日々の業務に追われて適切なコスト管理や節電対策が後回しになりがちなため、今こそ現状を把握し、早急な見直しが必要なタイミングとなっています。
特に、近年では省エネ設備更新や働き方の変化(テレワーク導入、営業時間短縮)なども電力コスト変動の新たな要素となっており、「今まで通り」の運用では電気代高騰への対策が追いつかなくなっている点も見逃せません。
電気代を見直すべき理由とは

経営数字に及ぼすインパクト
電気代は中小企業の経営に直接的な影響を与える固定費の1つです。特に生産現場や飲食、サービス業など、電力の使用量が多い業種では「月々数万円~数十万円単位での変動」が発生します。電気代の見直しによるコスト削減効果は、損益分岐点の改善やキャッシュフロー向上にも直結し、利益率の底上げや新たな投資原資の捻出につながります。
中小企業の利益状況別に、電気代削減インパクトの大きさを以下の表にまとめました。
| 企業タイプ | 年間電気代 | 電気代5%削減時の影響例 |
|---|---|---|
| 小規模オフィス(10人程度) | 約60万円 | 年間3万円の削減=備品購入や福利厚生の資金へ |
| 飲食店(店舗型) | 約120万円 | 年間6万円の削減=新メニュー開発費の一部へ |
| 製造業(中規模工場) | 約300万円 | 年間15万円の削減=機械設備の点検費用等に充当可能 |
「たかが数%」でも、経営全体へのインパクトが決して小さくないことがわかります。
多くの経営者が見落としがちなポイント
電気料金の明細を「ただ支払っているだけ」となってしまいがちですが、毎月の請求内容には経費削減につながる“ヒント”が隠れています。よくある見落としポイントは以下の通りです。
| 見落としがちなポイント | 内容 | 対策・見直し方法 |
|---|---|---|
| 契約アンペアや基本料金の見直し未実施 | 使用実態より多めに契約しているケース | 電力会社へ相談し、最適な契約容量に変更 |
| 最新の料金プラン・新電力の未検討 | 以前のまま従量電灯・従来型契約を継続 | 新電力・業務用プランの比較シミュレーション実施 |
| 時間帯別の使用量管理不足 | ピーク時に電気を多く使い基本料金が高止まり | 業務分散やピークシフト、省エネ機器導入の検討 |
| 省エネ投資のタイミング逃し | 古い蛍光灯・空調・冷蔵庫等を使い続けている | LED照明や高効率設備への更新、補助金活用 |
特に「契約容量・料金プラン・省エネ投資」の3点は見直しで大きな成果につながる可能性があります。また近年では東京都や中小企業庁、各地の商工会等による補助金・助成金制度も活用が進んでいます。目の前の請求書を「経営の視点」で改めて見つめ直し、コスト最適化につなげましょう。
中小企業が電気代を見直すためのステップ

電気代の見直しは、単なるコスト削減にとどまらず、中小企業の経営を持続的に安定させるための重要な施策です。以下のステップを踏むことで、実効性の高い見直しが可能となります。
現在の電気使用状況を「見える化」する
まず最初に行うべきは、自社でどれだけ電気を消費しているか正確に把握することです。検針票(電気料金明細書)から、月ごとの消費電力量や料金の推移を確認し、年間を通じた使用量の変動も整理すると、削減余地が明確になります。
最近では、スマートメーターやエネルギーマネジメントシステム(EMS)など電力可視化ツールも増えており、これらを活用することでリアルタイムの電力消費データ収集が可能です。
契約内容の確認と最適化(契約アンペア・電力プラン)
次に現在の電力契約の内容を確認します。契約種別(従量電灯B/C、低圧電力、高圧電力など)や契約容量(主にアンペア数)を把握し、実態に合っていない場合は最適化を検討しましょう。
| 主要な契約形態 | 特徴 | 見直しポイント |
|---|---|---|
| 従量電灯B/C(低圧) | 小型店舗やオフィス向け・30~120アンペア程度 | アンペア数の見直し・基本料金削減 |
| 低圧電力 | 店舗・事務所の動力設備向け | デマンド値調整・無効電力削減 |
| 高圧契約 | 工場・大型店舗など一定以上の需要家向け | 契約電力・力率の最適化 |
必要以上に高い契約容量や不適切なプランを利用し続けている場合は、即座に見直すことで大きなコスト削減効果が期待できます。
電気料金の比較~新電力・プラン切替の検討
2016年からの電力自由化により、中小企業も複数の小売電力(新電力)会社や料金メニューから最適なものを選択できるようになっています。現在契約している電力会社の他に、新電力会社への乗り換えや、より適したプランへの切り替えも積極的に検討しましょう。
主な新電力会社と選定ポイント
信頼性や料金メリット、サポート体制、再生可能エネルギー比率などを比較材料とし、自社の事業形態・規模にあった新電力会社を選びましょう。
| 新電力会社名 | 主な特徴 | 選定時の着目点 |
|---|---|---|
| Looopでんき | 基本料金0円・使った分だけ従量制料金 | 消費量が少ない/変動が大きい中小企業向け |
| ENEOSでんき | 安定供給力・グループ割引あり | ガソリンやオフィス燃料併用で割引活用可 |
| 東京ガスの電気 | 都市ガスとのセット割プラン | ガスと一元管理可能な企業におすすめ |
料金シミュレーションの具体例
電力各社の比較サイトや公式ホームページでは、過去の請求書データを入力するだけで、年間の支払い予測や現状との差額をシミュレーションできます。例えば、飲食店で月平均800kWh、契約容量30Aの場合、新電力Aは年間▲3万円、新電力Bは▲2万円といった差が出るケースも多く見られます。
まずは複数社でシミュレーションを行い、具体的にどれくらいの削減効果が見込めるかを必ず比較しましょう。
電気の使い方を工夫する省エネ対策
根本的なコストダウンには、日々の電力使用方法の見直しや省エネ行動も不可欠です。
LED化・空調の設定・業務機器の選択
照明のLED化は、従来の蛍光灯・白熱灯と比較し消費電力を50%以上削減でき、初期投資も価格低減により数年で回収可能です。
空調機器については、定期的なフィルター清掃やエアコン温度設定(夏28℃・冬20℃推奨)、タイマー活用などで稼働ロスを防げます。
業務用冷蔵庫・コピー機・パソコン等の事務機器も省エネ性能の高い新型への切替を進めることで、無駄な待機電力・消費電力の削減につながります。
補助金・助成金を活用する方法
国や自治体は、省エネルギー設備導入や新電力切替を支援する補助金・助成金制度を積極的に用意しています。代表的なものとして「省エネ補助金(経済産業省)」、「中小企業等経営強化法に基づく各種助成金」などがあります。
申請には、投資計画や効果見込みの提出が必須ですが、LED導入や高効率設備導入時の初期費用を最大1/2〜2/3程度補助する事例も多く、資金面での負担軽減・早期回収が期待できます。
実際の中小企業による電気代見直し事例
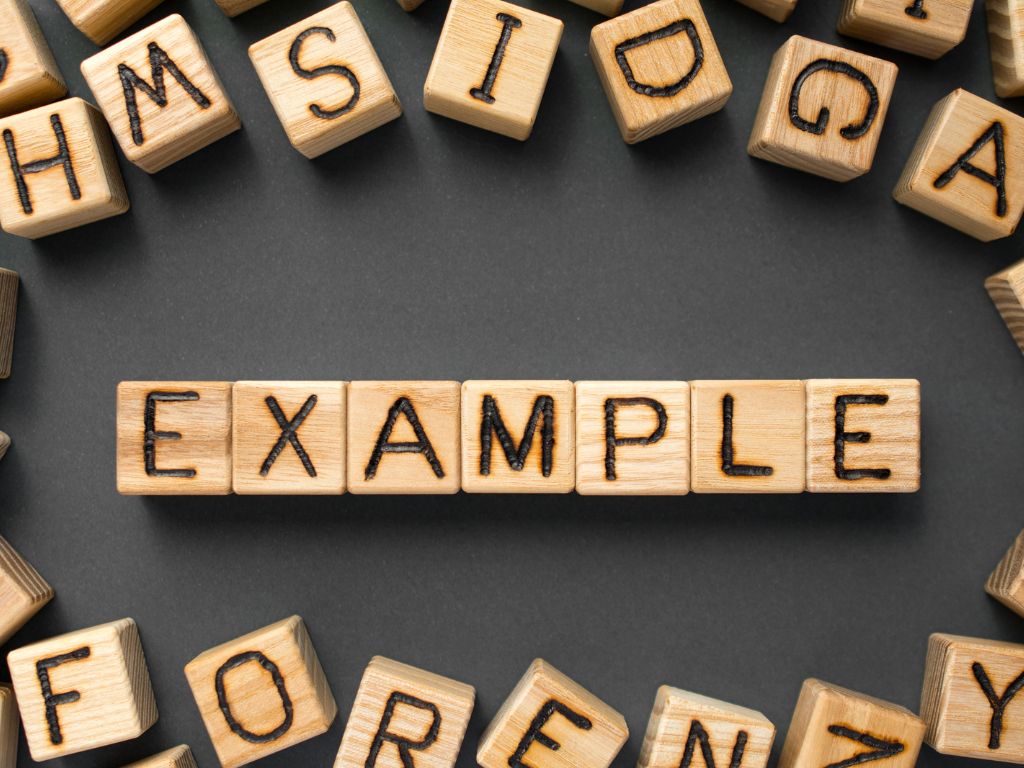
製造業での電気代見直し成功例
大阪府堺市に本社を構える金属加工業・ABC精密工業株式会社では、毎月の電気代が原材料費に次ぐ大きなコストとなっていました。電気使用量の可視化から着手し、夜間稼働機械の使用電力量を徹底管理。また昼休みや休日の機械待機電力の削減も実施しました。電力会社の乗り換えで新料金プランへ移行し、年間約15%のコスト削減を実現。その結果、削減できたコストを生産設備の省エネ改修や社員教育に投資でき、事業全体の競争力強化につながりました。
飲食業での省エネ・補助金活用事例
東京都内で3店舗展開する居酒屋チェーン「炉端焼き 田中」は、月々の光熱費の高さが経営課題でした。支出の見える化によってエアコンの無駄運転や照明・冷蔵庫の待機電力が判明。店舗全体でLED照明や高効率エアコンへ切替を進めました。また、経済産業省の省エネルギー補助金を活用し初期投資負担を軽減。1店舗あたり年間18万円、全体で約55万円/年のコストダウンに成功しました。従業員にも省エネ推進の意識が根付き、エネルギーコスト管理が経営の新たな軸となっています。
オフィスでの契約プラン最適化による成功例
IT受託開発を行う「株式会社サンネット」(名古屋市)は、社員数30名ほどの中小企業です。電力会社の見直しプロジェクトを始め、まず電力契約内容と使用パターンの精査を実施。契約アンペア数が過剰だったことが発覚し、アンペアダウンと「オフィス向け新電力プラン」に切替を行いました。同時に、社内のサーバー・ネットワーク機器の稼働時間見直し、省エネ型OA機器の導入も実施。これにより月間電気代を約20%削減でき、浮いた費用を人材育成や福利厚生の充実へ回せたとのことです。
コスト削減後のメリット
| 業種 | 実施内容 | 年間削減額 | 削減後のメリット |
|---|---|---|---|
| 製造業(ABC精密工業) | 料金プラン見直し・省エネ改善 | 約120万円 | 生産設備投資・競争力強化 |
| 飲食業(炉端焼き 田中) | LED・高効率エアコン導入 補助金活用 | 約55万円 | 収益率向上・従業員意識改革 |
| IT・オフィス(株式会社サンネット) | アンペア変更・新電力乗換・OA機器省エネ化 | 約24万円 | 人材投資・福利厚生充実 |
複数の業種で電気代見直しを実践した結果、単なるコスト削減だけでなく、設備改修や社員教育など経営資源への再投資、従業員の省エネ意識醸成、経営の収益力向上に波及していることが分かります。中小企業の環境変化に応じた持続的な成長戦略として、電気代見直しの取り組みは今後ますます重要になっていくでしょう。
電気代見直しを進める際の注意点とよくある質問

契約変更時の手数料やトラブルを避ける方法
電気代の見直しに際しては、契約内容の変更や新電力会社への切り替え時に発生する手数料やトラブルに注意が必要です。 多くの場合、契約期間の途中解約には違約金が発生するプランもあります。また、切り替え手続き時には現行契約の解約日と新規契約の開始日が重複しないようにすることが求められます。電力メーターの交換や工事が必要なケースもあり、日程の調整や立ち合いが発生することもあります。
契約変更における主な注意点を以下の表にまとめます。
| 注意ポイント | 具体的な内容 | 対策例 |
|---|---|---|
| 解約違約金 | 契約期間中に解約すると違約金が発生する場合がある | 契約約款を事前に確認し、違約金の有無と金額を把握 |
| 手数料 | 契約切り替えやメーター交換に手数料が発生することがある | 見積もり段階で手数料の有無を確認 |
| 切り替えタイミング | 契約の重複や空白期間が発生しないようにする | 新旧電力会社と日程を調整 |
| トラブル発生時の対応窓口 | 停電や請求ミスなどのトラブルが起こる可能性 | サポート体制が整った会社を選択 |
信頼できる電力会社の選び方
中小企業にとって安心して契約できる電力会社を選ぶことは、安定的な事業運営のために非常に重要です。 単に料金が安いという理由だけで選ぶのではなく、企業の信用度やサポート体制、実績など、複数の観点から比較検討することが求められます。
信頼できる電力会社を見極めるためのチェックポイントは以下の通りです。
- 会社の運営実績や顧客数を公開しているか
- 国や自治体からの業者登録や認可を受けているか(たとえば「資源エネルギー庁 登録小売電気事業者」など)
- サポートセンターが平日・休日にも対応しているか
- 料金プランや契約条件が明確に提示されているか
- 他社と比較した際の口コミや評判に問題がないか
- 緊急時や停電発生時の対応が明記されているか
これらを踏まえて、料金・契約条件・信頼性の三要素で総合的に選ぶようにしましょう。
BCP(事業継続計画)と合わせた電力見直し
災害や停電リスクが高まる中、電気代の見直しとともに事業継続計画(BCP)を策定することが重要です。 新電力会社によっては、大規模災害発生時の対応方針や復旧体制が大手と異なる場合があり、万が一の際のバックアップが不十分なことも考えられます。
中小企業がBCPとあわせて電気契約を見直す場合には、停電時の緊急対応策や、自社に必要なバックアップ体制を把握し、以下のようなポイントを押さえておくことが推奨されます。
- 重要設備には非常用電源・発電機の導入を検討
- 新電力会社の災害時対応力(復旧優先順位・補償範囲等)の確認
- 停電時の連絡体制や情報入手先を事前に整理
信頼性とコスト削減のバランスを取りつつ、会社の規模や業態に合った最適な電力見直しを実施しましょう。
よくある質問(FAQ)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 電力会社を切り替えても停電リスクは変わりますか? | 多くの場合、送配電設備は地域の送配電事業者(東京電力パワーグリッドなど)が維持しているため、切り替えても停電リスクは大きく変わりません。ただし、新電力会社との契約内容による補償範囲や復旧対応の違いは事前に調べましょう。 |
| Q. 切り替えによって電力供給が一時停止することはありますか? | 切り替え作業自体で電気が止まることは基本的にありませんが、まれにメーター交換工事が必要な場合は一時的な停電が発生することもあります。事前に必ず説明・案内があります。 |
| Q. 本当に電気料金の削減が見込めるのでしょうか? | 契約容量や使用状況によっては大きな削減効果があります。特に高圧受電や一般家庭向け契約からの見直し時に恩恵が大きいケースが多いです。事前に料金シミュレーションをおすすめします。 |
| Q. 新電力会社が倒産した場合はどうなりますか? | 小売電気事業者が倒産しても、「電力の供給継続義務」に基づき、地域の電力会社等に自動的に切り替わる制度がありますので、即時の停電や供給停止にはなりません。 |
| Q. 電力会社変更により、設備交換や工事費がかかりますか? | スマートメーターが未設置の場合、メーター交換が発生することがありますが、標準的には費用負担はありません。しかし、特殊工事が必要な場合は別途費用が発生する可能性もあるため事前に確認しましょう。 |
まとめ
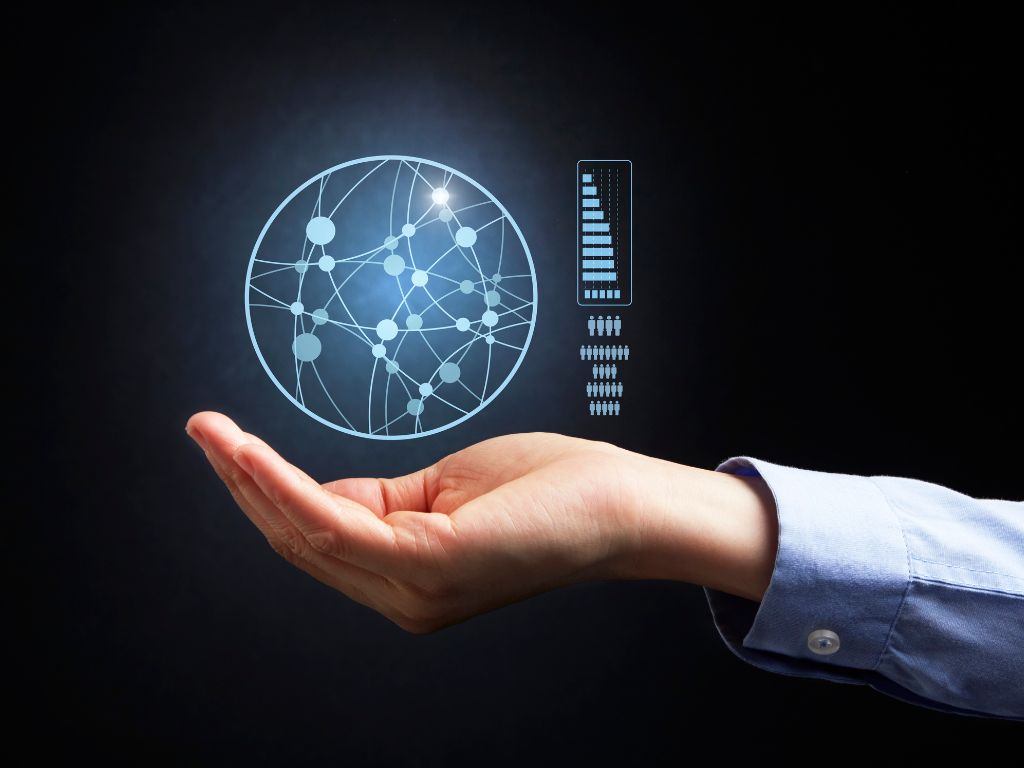
電気代の見直しは、中小企業の経営改善に直結する重要なテーマです。現状把握や契約内容の最適化、新電力会社の活用、省エネ対策、補助金利用を組み合わせることで、コスト削減のみならず収益改善・競争力強化も実現可能です。まずは「見える化」から取り組み、効果的な対策を進めましょう。