電気設備改修を検討しているが「どこから手を付けるべきか」「費用対効果はあるのか」と悩む方へ。本記事では、老朽化・省エネ対応・法令改正といった改修の背景から、コスト削減と安全性向上を同時に実現する効果的手法、そして成功事例までを科学的根拠をもとにわかりやすく解説します。
電気設備改修が必要とされる背景とは

老朽化による重大リスクの増加
電気設備は長年にわたり使用されることが多く、設置から10〜20年以上経過した設備では絶縁性能の低下や部品の劣化、接触不良などの問題が顕在化します。特に、古い配電盤や受変電設備などは、設置当時の安全基準や容量設計に基づいており、現代の電力需要に対応しきれないケースが増えています。
結果として、漏電・過電流による火災、停電、機械の故障といった重大な事故のリスクが高まり、企業活動や施設運営に深刻な影響を与える可能性があります。建物火災の原因の中でも「電気系統の不具合」に起因する割合は年々増加しており、予防保全の観点から電気設備改修は急務となっています。
省エネ・SDGs対応と電力効率の見直し
地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現に向け、日本国内ではエネルギー使用削減を積極的に進める必要があります。こうした背景の中で、省エネルギー性能を高めるための電気設備改修は企業や公共施設にとって取り組むべき重要事項となっています。
中でも、LED照明への切り替えや、高効率な空調・照明制御システム導入によって、消費電力を大幅に削減できる可能性があり、SDGs(持続可能な開発目標)の達成や環境マネジメント(ISO14001など)の観点からも有益です。また、政府が推進する「グリーントランスフォーメーション(GX)」や「エネルギー基本計画」においても、省エネのための設備更新が強調されています。
法令改正に伴う対応義務の増加
電気設備に関する法律や政令、省令も定期的に改正されています。例えば、「電気設備技術基準の解釈」や「建築基準法」、「労働安全衛生法」における規定が見直されるなど、法的な要件を満たすための電気設備更新が必要になるケースが後を絶ちません。
特に以下のようなポイントが、法令改正によって対応を迫られる主な内容です。
| 改正年 | 対象法律 | 主な改正内容 | 影響を受ける主な設備 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 電気設備技術基準 | 接地工事のグレード見直し | 配電盤・接地設備 |
| 2017年 | 建築基準法 | 非常用発電設備の設置義務の追加 | 非常用電源、照明設備 |
| 2020年 | 省エネルギー法 | エネルギー消費量報告の強化 | BEMS、電力量監視装置 |
| 2022年 | 労働安全衛生法 | 感電保護装置の設置義務化 | 漏電遮断器、保安器具 |
これらの改正は、単なる設備の修繕を超えた「法的適合性の確保」や「事業継続性の担保」を意味しており、対応を怠ると罰則のほか、事故発生時の法的責任・損害賠償リスクにも繋がります。
電気設備改修の主な対象部位とトレンド

配電盤・分電盤の交換と更新
配電盤や分電盤は電力の供給を各設備へと分配する中枢であり、老朽化や絶縁不良、遮断器の動作不良などを放置すると火災や停電といった重大事故につながるリスクがあります。現行の電気設備基準に則った新型配電盤への更新は、安全性の向上と事業継続性の確保に直結します。
また、近年ではスマート計測機能やIoT連携に対応した“スマート分電盤”が登場しており、内部回路の過負荷状況や漏電を常時監視することが可能になっています。これにより、予防保全型の運用が実現できるため、保守コストの最適化にも寄与します。
LED照明への切り替えによるコスト削減
施設照明のLED化は、エネルギーコスト削減という面から非常に効果的です。消費電力が一般蛍光灯と比べて3分の1〜5分の1に抑えられるうえ、寿命が4万〜6万時間と長寿命であるため、ランニングコストの低減とメンテナンス頻度の大幅減が期待できます。
加えて、スケジューラーや人感センサーと併用することにより、タイムマネジメントや照度調整による省エネ運用も可能になります。LED化は、省エネ法・建築物省エネ法への適合という観点からも推奨されており、公共施設や病院、商業施設を中心に導入が加速しています。
受変電設備の高効率化と自動化
受変電設備は、自社施設へ供給される高圧電力を適切な電圧へ変換・制御するための重要インフラです。経年劣化により電力ロスやトラブルが増加するため、定期的な更新は不可避です。
近年では、以下のような高効率・高信頼性の機器へのリプレースが進行しています。
| 更新対象設備 | 主な導入トレンド | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 受電用変圧器 | 低損失型変圧器(アモルファス鉄心など) | 電力ロスの削減・電力使用効率の向上 |
| 開閉器 | パワーMOSFET・IGBTなどデジタル制御型 | 応答性向上・省スペース化 |
| 配電保護装置 | スマートブレーカ・高性能遮断器 | 事故検知精度の向上・瞬時切替対応 |
さらに、ALS(自動負荷切換装置)や高機能PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を用いた自動制御も併用され、電力供給の安定化と即時障害対応が可能になっています。
監視システムとBEMSの導入
BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)は、建物内のエネルギー使用状況を常時監視・制御できる仕組みであり、電気設備改修における高度運用の鍵となります。
温度・湿度・照度・在席状況など複数のセンサーと連動し、空調・照明・換気設備を統合管理できるようになります。これにより、以下のようなメリットが得られます。
- エネルギーロスの原因特定とピンポイント対応
- ピーク電力量の抑制とデマンド管理の自動化
- 月次レポートによるエネルギー監査とPDCA改善
BEMSは、経済産業省が推進するZEB化(Net Zero Energy Building)を実現するための中核技術であり、今後のエネルギー政策との整合も取りやすく補助金支援も受けやすい特徴があります。
効果的な電気設備改修とは何か
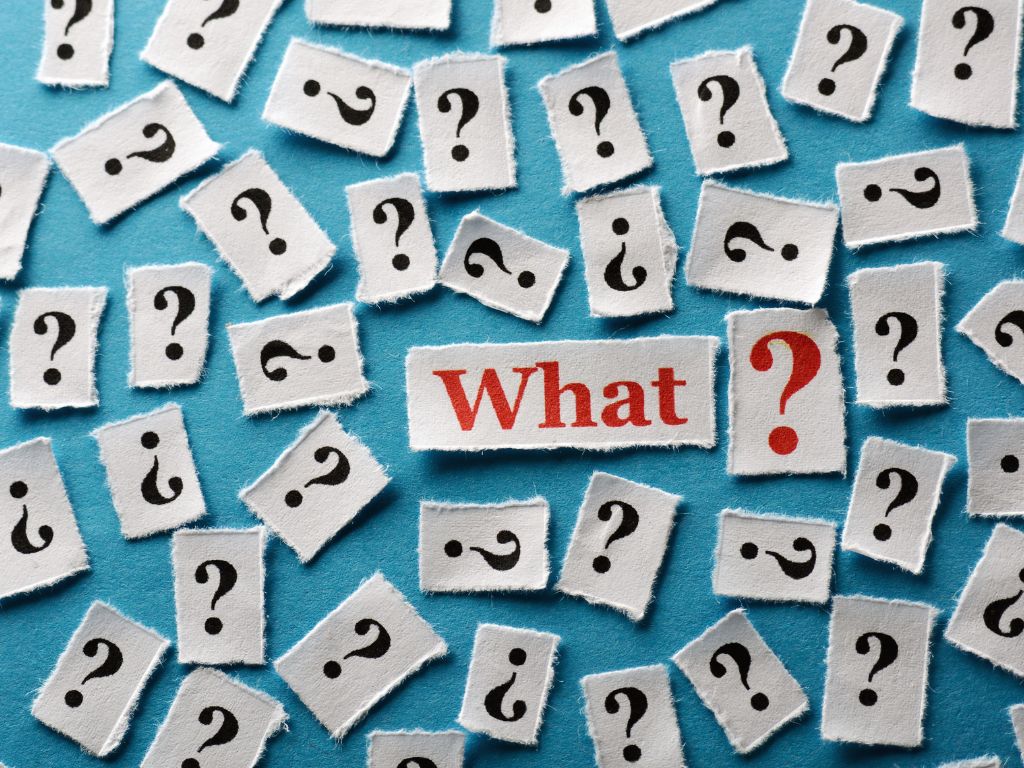
診断・調査による現状把握の重要性
電気設備改修を効果的に進めるためには、まず現在の設備の性能や劣化状況、法令適合性を正確に把握することが不可欠です。建築物の竣工から10年以上が経過している場合は、経年劣化によるリスクが増加しており、トラブルを未然に防ぐためにも診断・点検が必要とされます。一般的には、建築設備定期検査や年次点検、精密診断(絶縁診断、熱画像診断など)を併用して総合的に評価します。
以下のような調査項目を系統的に実施することで、改善が必要なポイントを明確にできます。
| 調査項目 | 目的 | 主な手法 |
|---|---|---|
| 絶縁診断 | 漏電・短絡リスクの可視化 | メガオーム計による測定 |
| 熱画像診断 | 異常発熱箇所の検出 | サーモグラフィカメラによる熱画像分析 |
| 電力量分析 | ピーク時の負荷状況把握 | 電力計測器によるデータ収集 |
| 法令適合調査 | 電気設備技術基準・消防法などへの対応確認 | 書類照合、現地確認 |
加えて、設計図書との整合性確認も行うことで図面と実態の齟齬を洗い出し、改修計画を正確に策定可能です。
ライフサイクルコストを考慮した投資判断
改修工事を検討する際には、初期費用のみに目を向けるのではなく、ライフサイクルコスト(LCC:Life Cycle Cost)を踏まえた中長期的な視点による投資判断が重要です。LCCとは、設備の導入から廃棄に至るまでの全費用を指し、電気代、保守点検費、部品交換費、法定改修費なども含まれます。
例えば、LED照明器具に更新する場合、初期投資こそ必要ですが、消費電力や保守コストが従来の蛍光灯に比べて大幅に低下し、数年で投資回収が可能となります。また、受変電設備など長寿命機器は、機器製造終了による修理不能リスクや性能陳腐化からくるエネルギー効率の低下を考慮し、更新のタイミングを検討します。
LCC評価の際は、以下の算出項目を整理すると経済性比較が容易になります。
| 分類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 設計、機器代、施工費 | 導入時の一時的支出 |
| 運転・保守費 | 点検費用、定期交換費 | 年次更新費を含む |
| エネルギー費 | 電力料金 | 高効率化により削減可能 |
| 更新・廃棄費 | 寿命後の解体撤去費用 | 最終処分や再整備コストに注意 |
このように、トータルコストを見据えた上で設備選定・時期判断をすることで、高効率かつ持続可能な設備運用が可能となります。
段階的な改修計画とスケジューリング
大型施設や稼働中の事業所においては、一度に全設備を更新することが難しく、段階的かつ戦略的な改修スケジュールの策定が効果的です。これにより、予算の平準化、稼働停止リスクの低減、技術導入の柔軟性確保といった複数のメリットが得られます。
改修を段階化する際のポイントとして、以下の観点で優先順位を付けることが重要です。
- 安全性の観点から緊急性の高い設備(絶縁劣化、過熱など)
- 故障時の事業影響が大きい重要系統(受変電設備、制御盤など)
- 省エネルギー効果が大きく投資対効果が見込まれる機器(モーター、空調/照明)
また、月別・季節別のエネルギー消費や稼働予定も考慮し、工事のタイミングを適切に設定することが求められます。例えば、工場では生産調整可能な長期連休中(ゴールデンウィークや年末年始など)を活用した改修が望ましいとされます。
さらに、改修工程を全体マップとして管理する「マスタースケジュール」を作成し、工程進捗を定期的にレビューすることで、工事遅延・費用超過のリスクを最小限に抑えることができます。
コスト削減を実現するための手法
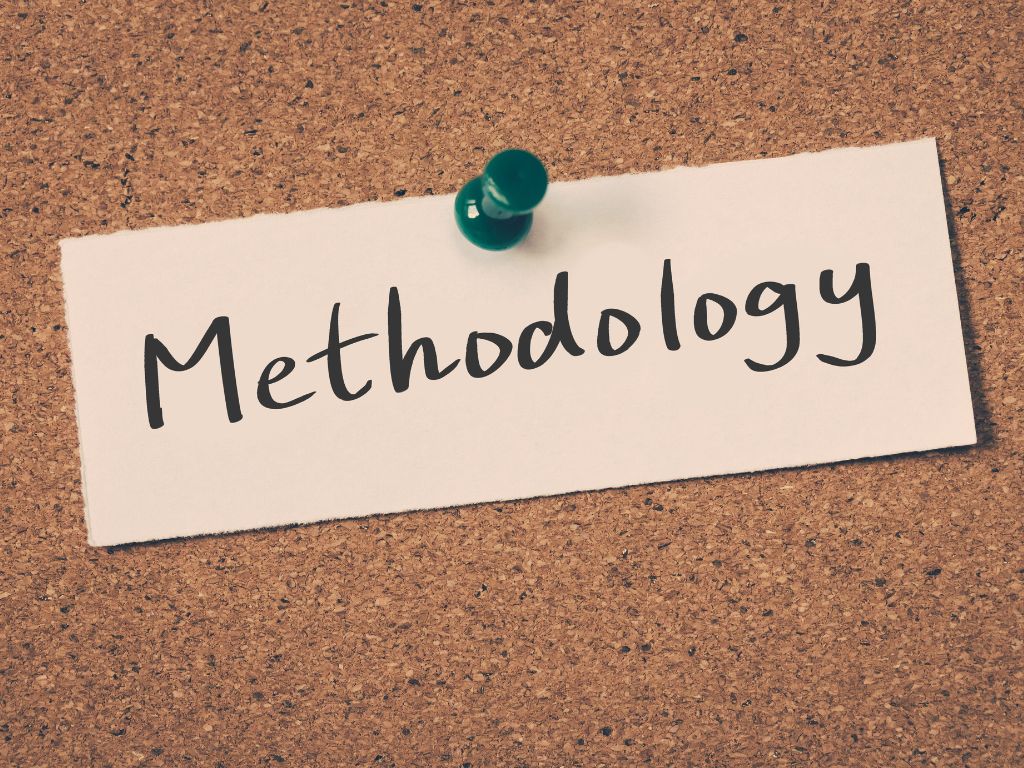
補助金・助成金の活用方法例(例:エネ合・省エネ補助金)
電気設備改修を行う際、各種補助金や助成金を適切に活用することで初期投資を大幅に抑えることが可能です。特に経済産業省や環境省の主導により実施されている「先進的省エネルギー投資促進支援事業(通称:エネ合)」や、「省エネルギー設備導入補助金」などは、中小企業から大規模事業所まで幅広い施設が対象となります。また、自治体が独自に実施する補助制度も存在し、地域に応じたサポートを受けることもできます。
申請時には、補助対象となる設備(LED照明、高効率変圧器、自動制御システムなど)や事業規模、費用対効果の算出など、詳細な計画書とエネルギー削減効果のデータ提出が求められるため、事前準備が重要です。
| 補助金名 | 主な対象設備 | 補助率 | 実施機関 |
|---|---|---|---|
| エネ合(先進的省エネルギー投資促進支援事業) | 高効率照明、インバータ設備、EMS導入 | 最大1/2 | 経済産業省・環境共創イニシアチブ(SII) |
| 省エネルギー投資補助金(地方自治体) | LED・空調更新・BEMSシステム | 1/3〜1/2(自治体による) | 都道府県・市区町村 |
必要な費用を抑えながら効果的な設備更新を進めるためには、これらの制度の活用が極めて有効です。建物や事業の特性に応じた適切な補助金の選定と申請スケジュール管理が成功の鍵となります。
IT技術を活用したエネルギー管理(IoT・EMS連携)
近年では、電気設備の管理および効率的運用においてIoT(モノのインターネット)とEMS(エネルギーマネジメントシステム)の活用が注目されています。これにより施設内のエネルギー消費状況のリアルタイム可視化、異常の早期発見、使用ピークの予測などが可能となり、無駄な電力使用を抑制できます。
例えば、タイムリーなデータ収集を可能とするスマートメーターやセンサーを分電盤や主要機器に設置することで、エネルギーロスの発生箇所を明確化し、改善策を立てやすくなります。これにより、継続的かつ具体的なコスト削減につながります。
また、BEMS(ビルエネルギー管理システム)と連携した制御により、照明の自動調整や空調の最適化も行え、人的管理負担の軽減にも効果的です。
電力量モニタリングと使用パターンの最適化
電力使用状況を日単位・時間単位で細かくモニタリングすることで、ピークシフトやピークカットを実現できます。これにより基本電力料金を下げることが可能となり、特に契約電力が高く設定されている事業所では大きなコストインパクトをもたらします。
このような分析には、デマンド監視システムの導入が非常に有効です。一定時間内の最大需要電力(デマンド値)を記録・管理することで、設備改修だけでなく運用方法の見直しによる間接的なコスト削減も図れます。
加えて、需給調整の制度(ネガワット取引など)の対象施設として登録することで、電力会社から報酬を得ることが可能なケースもあり、エネルギー管理は大きな経済的メリットにつながります。
機器の改修だけではなく、「いつ・どこで・どれくらい電気を使っているか」を把握することがコスト削減の第一歩であるという認識が現場に根付くことで、継続的な改善活動が可能となります。
安全性向上に寄与する電気設備改修の手法

過負荷・漏電防止装置の最新規格対応
現代の電気設備環境では、機器の高機能化・高負荷化に伴い、過電流・漏電リスクが増大しています。これに対処するため、配電経路に設置される漏電遮断器や過負荷保護装置を最新のJIS規格、またはIEC規格に準拠した製品へ更新することが重要です。
とくに感度電流・動作時間の調整が可能なデジタルタイプの漏電遮断器は、従来型に比べて誤作動が少なく、建物の安定稼働への寄与度が高くなっています。また、定期点検が困難な高所や屋外用の配電盤には、自己診断機能付き遮断器や、遠隔から状態監視が可能な製品の導入が推奨されます。
さらに、絶縁監視装置を併設することで、漏電の予兆段階から異常を正確に把握でき、機器の損傷や火災のリスクを未然に防ぐ仕組みが構築可能です。
地震対策を意識した設備設計と施工
日本は地震大国であり、電気設備にも高度な耐震性能が求められます。そのため、受変電設備や配電盤、非常電源などを対象に、地震動に耐えられる耐震設計及び固定工法を前提とした改修が不可欠です。
国土交通省が定める「建築設備耐震設計・施工指針」や「電気設備技術基準」などに準拠し、適切なアンカー固定、免震架台の使用、重心バランスの配慮を行うことで、地震時における二次災害リスクを大幅に低減できます。
以下は、主要な設備と耐震化の推奨対策例です。
| 対象設備 | 耐震化推奨対策 | 関連基準 |
|---|---|---|
| 受変電設備 | 専用耐震架台設置、機器重心調整 | 建築設備耐震設計・施工指針(AIJ) |
| 分電盤・配電盤 | アンカー固定+振動吸収材設置 | 電気設備技術基準 解釈第36条 |
| ケーブルラック | 揺れ止め支持金具の強化 | 内線規程 JESC E0001 |
| 自家発電装置 | 基礎連結・仕切りの設置 | 消防法施行規則第9条 |
また、改修時には点検歩行の安全確保、照明の落下防止、避難誘導灯の耐震固定なども並行して実施することが望ましく、電気設備全体の災害対応力を高めるために建築構造体との一体的なアプローチが求められます。
停電・災害時のBCP対策としての自家発電システム導入
企業や公共施設が停電時でも事業・サービスを継続できるよう、BCP(事業継続計画)の観点から自家発電設備の導入・更新が安全性改善の要となっています。
特に、重要負荷(照明、防災設備、サーバー、医療機器など)への電源供給を維持するために、非常用発電機や無停電電源装置(UPS)を電気設備に組み込むことが有効です。以下は主な保安電源設備の特徴です。
| 設備種別 | 主な用途 | 稼働時間目安 |
|---|---|---|
| 非常用ディーゼル発電機 | 建物全体・消防設備・エレベーター | 8~24時間(燃料保有量による) |
| UPS(無停電電源装置) | 情報機器・サーバー保護 | 数分~数時間(バッテリー容量による) |
| ガスコージェネレーション | 熱電併給、長時間稼働に対応 | 燃料供給継続で数日稼働可能 |
また、運用効率を高めるには、自家発電装置の自動始動機能、常時監視システム(遠隔監視・保守)、定期試運転の計画的実施が必要です。自治体や業界団体による補助制度(例:事業継続強化計画認定制度)を活用し、災害に強い電気インフラ整備を加速させることも重要な方策となります。
導入事例から学ぶ改修成功のポイント

オフィスビルにおける受変電設備リニューアル
東京都心に位置する築30年の中規模オフィスビルでは、老朽化した受変電設備を最新の高効率モデルに更新することで、電力ロスの軽減と保守費用の削減を同時に実現しました。改修前は、定期的なトラブルや部品調達の困難さが課題となっていましたが、改修後には年間で15%以上の電力使用量削減を達成。あわせて、スマートメーターと監視システムを導入し、運用状況を常時モニタリングできる体制を構築しています。
施工中の停電対策としては、夜間および休日の作業スケジュールを徹底的に管理し、テナントの業務に支障をきたさないよう配慮しました。また、補助金制度(東京都の建物の省エネ診断支援事業)を活用し、初期投資コストの20%をカバーしたことで早期の費用回収も可能となった事例です。
工場での高圧設備更新による稼働効率アップ
愛知県にある自動車部品製造工場では、老朽化した高圧受電設備のトラブル頻度増加と生産ライン停止のリスクを懸念し、第1種電気工事士による計画的な高圧配電盤・変圧器の更新を実施しました。この更新により、突発的な停電や設備ダウンのリスクが大幅に低減。
加えて、省エネルギー化を目的に導入した高効率変圧器(トップランナー変圧器)は、CO₂排出量削減にも貢献。年間約8トンの削減効果が得られ、企業の環境配慮型経営の一環として社外からの評価も向上しました。
以下はこの工場における改修効果の概要です。
| 項目 | 改修前 | 改修後 | 改善効果 |
|---|---|---|---|
| 保守トラブル頻度 | 月平均3件 | 月平均0.5件 | 約83%削減 |
| 年間電力使用量 | 1,200,000kWh | 1,050,000kWh | 12.5%削減 |
| 電力料金 | 約2,400万円 | 約2,100万円 | 年間約300万円削減 |
| CO₂排出量 | 65トン | 57トン | 約8トン削減 |
病院施設での停電対策強化事例
神奈川県内の総合病院では、災害時の医療継続体制強化の必要性から、非常用自家発電設備と無停電電源装置(UPS)を併用したBCP対策を実施しました。この病院は年間60万人以上の外来患者数を誇り、急な停電は命に関わるリスクを孕んでいます。
今回の改修では、最新のディーゼル発電機(定格出力500kVA)の導入により、最大で24時間の電力自給が可能となりました。さらに手術室、ICU、ナースステーションなど優先度の高いエリアにはUPSを設置し、瞬時に電力供給を可能にしています。
この改修の結果、内閣府の地域防災計画において「防災拠点医療施設」に指定されるまでに至り、地域貢献と同時に病院としての信頼性が格段に向上しました。
また、施工にあたっては特別高圧設備の資格を持つ施工業者がプロジェクトを担当し、安全管理者の常時配置、綿密な断電計画、安全書類の可視化と共有など、医療現場に特化した高い安全基準が守られました。
電気設備改修を進める上での注意点

資格ある電気工事士による施工
電気設備の改修は専門性が極めて高く、感電や火災のリスクも伴うことから、法的に定められた資格を有する電気工事士による施工が必須です。低圧の電気設備工事では「第二種電気工事士」、高圧受電設備などの改修には「第一種電気工事士」の資格が必要です。
また、電気主任技術者や建築設備士といった補助的な技術者との連携も重要です。改修対象となる設備の規模や内容に応じて、適切な資格者による配置計画を立てることで、工事の品質と安全性を担保できます。
施工時の断電計画と影響最小化
電気設備の改修では、一時的な停電(断電)が事業活動に与える影響をいかに最小限に抑えるかが極めて重要なポイントです。特に病院、データセンター、生産ラインを有する工場など、電力供給の停止が大きな損失につながる施設では、改修スケジュールの立案段階から緻密な断電計画が求められます。
主な対応策には以下のようなものがあります。
| 対応策 | 概要 |
|---|---|
| 夜間・休日工事 | 施設の利用が少ない時間帯を選んで工事を実施し、業務への影響を抑える。 |
| 仮設電源の設置 | 臨時の発電機や非常用電源を準備して、必要な時間帯のみ切り替える。 |
| 部分断電方式 | エリアごとに段階的に改修を実施し、施設全体の停止を回避する。 |
これらの手法により、利用者や顧客、従業員などへの影響を最小限にとどめつつ、効率的な工事推進が可能になります。
信頼できる業者の選び方と見積比較
電気設備改修の成否は、実際に施工を行う業者の技術力、実績、対応力に大きく依存します。よって、信頼性の高い専門業者を慎重に選ぶプロセスが不可欠です。
優良な業者を選ぶためのチェックポイントは以下の通りです。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 資格・許可の有無 | 電気工事業の登録や建設業の許可があるか。 |
| 過去の実績 | 自社と同規模または同業種での施工経験があるか。 |
| 保守・点検体制 | 改修後の定期点検や緊急対応が可能か。 |
| 第三者評価 | 口コミや顧客満足度、自治体からの受注実績。 |
また、複数の業者からの見積もりを取り、価格だけでなく提案内容まで含めて比較検討することも重要です。単に安価な業者を選ぶのではなく、「提案力」「説明力」「リスク対策の明示」なども評価軸に入れることで失敗のない導入につながります。
自治体や大手民間施設のプロジェクトにも多数関わっているような業者は、技術力・対応力の両面で安心感があります。そのような背景も踏まえた選定が、中長期的に安定した電気設備運用を実現します。
まとめ

電気設備改修は老朽化対策や省エネ、法令対応だけでなく、コスト削減と安全性向上を同時に実現する重要な取り組みです。信頼できる業者による計画的な診断と施工、最新の設備導入や国の補助金活用により、長期的な経済性と持続可能性の両立が可能となります。