停電が発生してからでは間に合わない、生活やビジネスの安全を守るためのバックアップ電源。この記事では、増加する自然災害による停電リスクやその被害、バックアップ電源の必要性と実際の導入コスト、選び方や補助金制度の活用法まで、正しく備えるための全知識を分かりやすく解説します。
停電の現状とバックアップ電源の需要動向
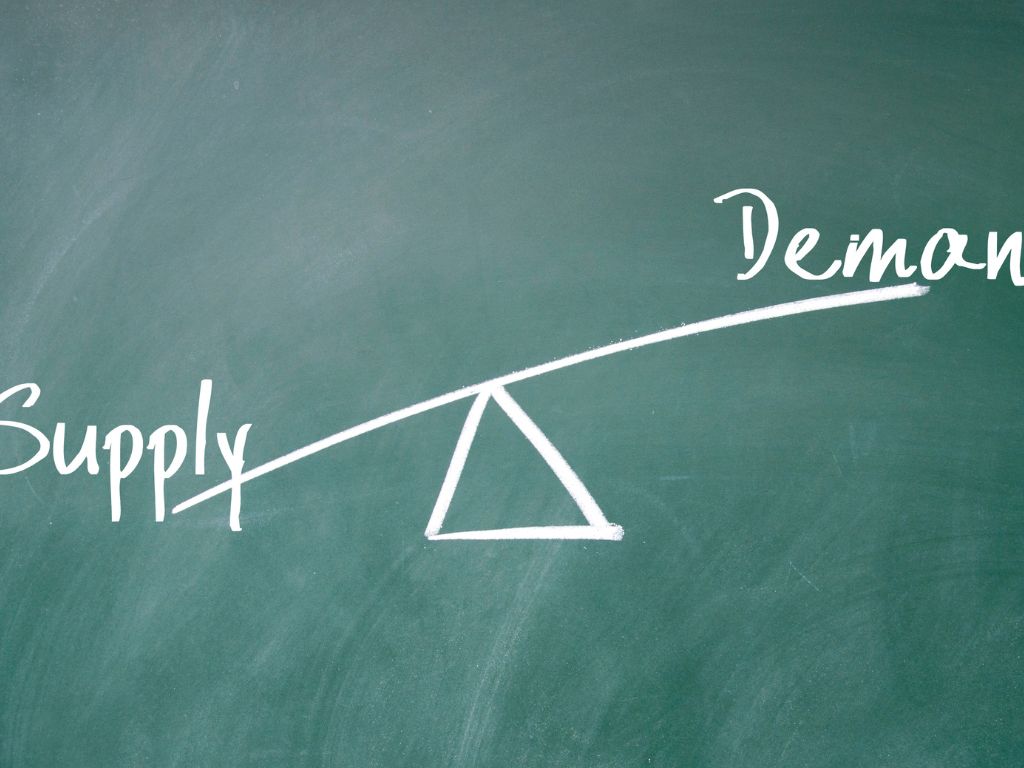
近年増加する自然災害がもたらす停電リスク
日本は四季折々の美しさに恵まれる一方で、地震・台風・集中豪雨・落雷といった自然災害の頻発地域でもあります。これらの自然災害により、広範囲かつ長時間にわたる停電が増加傾向にあります。特に近年では、2018年の北海道胆振東部地震、2019年の台風15号や台風19号による大規模停電が発生しています。日本全国で停電発生件数は年々増加しており、瞬時電圧低下や長時間停電が事業活動や生活に深刻な影響を与えています。
| 発生年 | 主な原因 | 停電戸数(最大時) | 主な被害地域 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 北海道胆振東部地震 | 約295万戸 | 北海道 |
| 2019年 | 台風15号 | 約93万戸 | 千葉県中心 |
| 2019年 | 台風19号 | 約52万戸 | 関東・東北地域 |
| 2021年 | 大雪・落雷 | 約20万戸 | 関西・北陸地方 |
また、気象の極端化や老朽化インフラの影響で、停電の頻度・規模ともに今後さらなる拡大が懸念されています。各電力会社も復旧体制強化を図っていますが、広範囲災害時は速やかな復旧が難しい場合も多くなっています。
家庭とビジネスにおける停電による被害事例
停電は家庭だけでなく、ビジネスの現場でも甚大な影響を及ぼします。家庭では冷蔵庫内の食品腐敗や、テレビ・インターネットといった情報インフラの一斉停止、給湯・空調の不具合など生活全般に直結し、高齢者や乳幼児のいる世帯では健康被害リスクすら生じます。
一方、オフィスや工場等ビジネス施設では、生産ラインの停止やパソコン・サーバーのデータ消失、POSや電算システムの遮断によって、売上の損失や重要データの消失、業務全体の遅延・混乱といった実害が発生しています。特に医療機関では、人工呼吸器やICU機器への電力供給停止が人命被害につながるため、停電リスク軽減は社会的な要請となっています。
| 分野 | 具体的な被害例 | 発生時の影響 |
|---|---|---|
| 家庭 | 冷蔵庫の食品腐敗、エアコン停止、電話・携帯充電不可 | 食品廃棄、健康被害、情報遮断 |
| 店舗・オフィス | POS/レジ停止、照明・空調停止、パソコン・サーバーダウン | 営業停止、データ消失、顧客対応不能 |
| 医療機関 | 医療機器の動作停止、検査装置ダウン | 診療不能、命に関わるリスク |
| 工場 | 生産ライン停止、監視システム障害 | 生産遅延、品質トラブル |
こうした背景から、一時的な停電であっても社会・経済活動の停滞リスクが高まり、事前対策となるバックアップ電源への需要は急速に高まっています。実際、家庭・法人を問わず災害時への備えを強化する動きが見られ、蓄電池やUPS、発電機などの導入検討件数や販売台数も年々増加傾向となっています。
バックアップ電源が果たす重要な役割
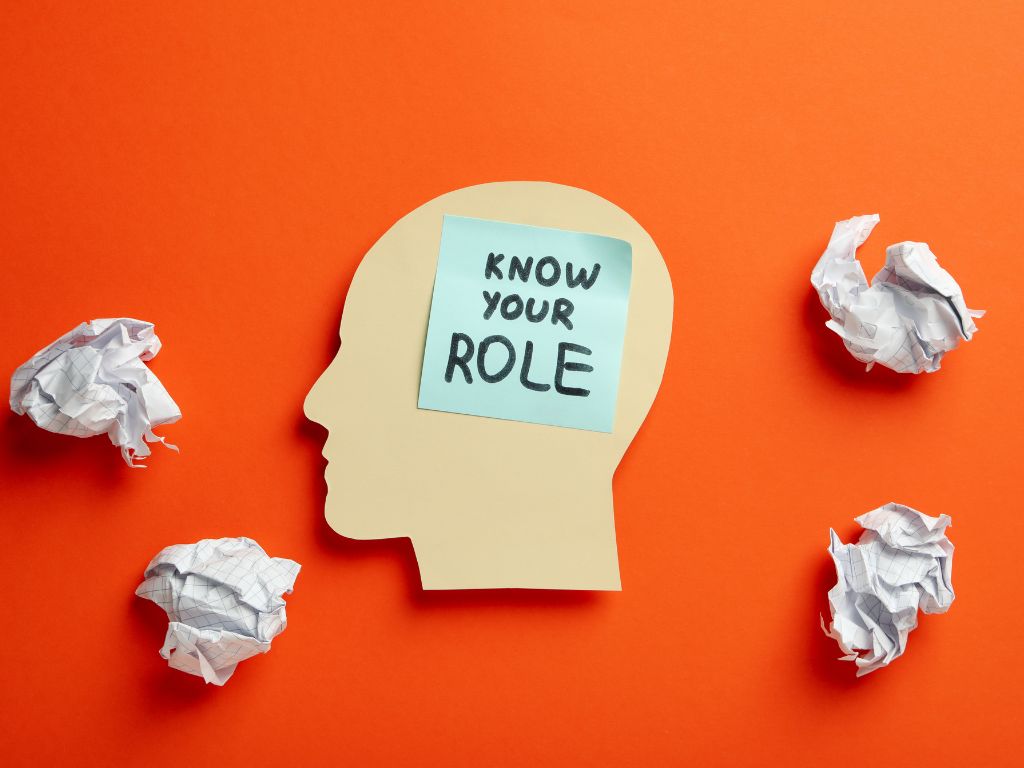
非常時に求められる「備え」としての電源確保
停電は突然発生し、私たちの生活や事業活動に大きな影響を与えます。バックアップ電源は、非常時における「命綱」として大切な役割を担っています。自然災害や送電トラブルなどで停電が発生した際、冷蔵庫や照明などの生活必需品から、暖房・冷房機器、防犯設備など様々な機器の稼働を維持することで、被害拡大や不安の軽減につながります。特に冬季や夏季の厳しい気候下では、熱中症や低体温症を防ぐためにも電源確保は欠かせません。
また、昨今ではテレワークの普及に伴い、自宅でパソコンやインターネットを利用している人も多く、自宅のネット環境や情報端末を守るためにも、バックアップ電源の重要性が増しています。
医療機器やIT機器など止められない機器との関係性
一定の電力供給が止まることによって重大なトラブルにつながる機器も多く存在します。特に在宅医療で利用される酸素濃縮器や人工呼吸器など生命維持に不可欠な医療機器は、一瞬の停電であっても危険を伴います。そのため、これらの機器を使っている家庭や医療施設には、導入義務や推奨がなされている場合もあります。
また、ビジネス現場では、パソコン・サーバー・ネットワーク機器などのIT機器も、予期しないシャットダウンによるデータ損失やシステム障害を防ぐ必要があります。UPS(無停電電源装置)や家庭用蓄電池、ポータブル電源の導入によって、重要なデータやサービスの継続を可能にし、事業の信頼性を確保できます。
| 用途 | 停電時のリスク | バックアップ電源の役割 |
|---|---|---|
| 医療機器(在宅・クリニック) | 生命維持機能停止の危険 | 長時間の安全稼働を保証 |
| IT機器・サーバー | データ消失・業務停止 | 安全なシャットダウンや継続稼働が可能 |
| 生活家電 | 食品腐敗・健康被害・セキュリティ低下 | 最低限の生活インフラを保持 |
| 防犯設備・通信機器 | 防犯機能停止・孤立化の危険 | 常時通報・連絡手段の確保 |
停電がもたらすリスクは多岐にわたり、バックアップ電源は「安全」「安心」「継続」の実現に欠かせない存在です。導入時は自分たちにとって停止しては困る機器やシステムを洗い出し、必要な設備の選定と適切な維持・管理が求められます。
バックアップ電源の種類と特徴

停電に備えて導入されるバックアップ電源にはさまざまな種類があり、それぞれ利用シーンや用途、必要な容量、設置方法などに違いがあります。ここでは、代表的な4つのバックアップ電源について、その特徴と選び方のポイントを詳しく解説します。
ポータブル電源
ポータブル電源は、持ち運びができるバッテリー式電源装置です。小型で軽量な製品が多く、アウトドアや車中泊、非常時の一時的な電源確保に適しています。スマートフォンやノートパソコン、照明器具といった消費電力の小さい機器を中心に使う場合に向いています。近年では容量が拡大し、IH調理器や小型冷蔵庫を動かせるモデルも登場しています。リチウムイオン電池を内蔵し、太陽光パネルから充電できるタイプも人気です。
| 主な用途 | 容量の目安 | 充電方法 |
|---|---|---|
| スマートフォン・照明・小型家電 | 200Wh〜2000Wh | 家庭用コンセント・車・ソーラー |
家庭用蓄電池
家庭用蓄電池は、住宅に設置して家庭全体や重要回路へ電力供給を行える大型のバックアップ電源です。多くは壁掛けや床置きの固定式で、家庭用分電盤と接続して停電時に主要な家電を長時間使用できる点が大きな特長です。太陽光発電システムと連携したハイブリッド型も多く、日常の節電・ピークカット対策としても活躍します。出力が高く、エアコンや冷蔵庫などの家電にも対応できるのが強みですが、設置工事と初期費用が必要です。
| 主な用途 | 容量の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 住宅全体・重要家電のバックアップ | 4kWh〜12kWh | 太陽光発電との連携可 |
UPS(無停電電源装置)
UPS(無停電電源装置)は、パソコンやネットワーク機器、医療機器などの機器を瞬時にバックアップし、瞬間的な停電や電圧変動から機器のデータやシステムを保護する装置です。小型のデスクトップ用からサーバールーム用の大容量モデルまで多様なラインアップがあります。停電時にはバッテリーから電力が供給され、一定時間安全にシャットダウンしたり、長時間運転が必要な場合は大型製品を選ぶ必要があります。
| 主な用途 | 容量の目安 | バックアップ時間 |
|---|---|---|
| パソコン・ネットワーク・医療機器 | 500VA〜10kVA以上 | 数分〜数十分 |
発電機
発電機は、ガソリンやカセットボンベ、ディーゼルなどの燃料を用い、自力で電力を作り出す装置です。大容量のバックアップや長時間運転、屋外や工事現場、イベントなど幅広い用途で活用されています。住宅への設置の場合は、騒音・排気・保管方法など安全面の配慮が必要ですが、自然災害など長期間の停電時にも対応できる非常時の強い味方となります。最近は、操作が簡単なインバーター発電機や、エンジン式の本格モデルなど各種タイプが流通しています。
| 主な用途 | 出力の目安 | 燃料の種類 |
|---|---|---|
| 工場・屋外作業・非常用電源 | 0.5kVA〜10kVA以上 | ガソリン・カセットガス・ディーゼル |
このように、それぞれのバックアップ電源には特徴や適した用途があります。ご家庭やオフィスでの停電対策には、利用目的や必要な容量、設置環境を考えて、最適なタイプを選ぶことが大切です。
バックアップ電源導入時に考慮すべきポイント

必要な容量・想定利用シーンの想定
バックアップ電源を導入する際には、まず「どの機器に」「どれくらいの時間」電力を供給したいのかを明確にすることが重要です。例えば、家庭であれば冷蔵庫や照明、携帯電話の充電、ビジネスの場合はパソコンやサーバー、通信設備など、停電時に絶対に止めたくない機器をリストアップしましょう。その機器の消費電力(W数)と必要なバックアップ時間を掛け合わせることで、必要なバッテリー容量(Wh)が算出できます。必要な容量の見極めが不足していると、「いざという時に使えない」「容量オーバーですぐ落ちる」といったトラブルの原因となります。利用シーンのシミュレーションをすることが失敗しない選び方の鍵です。
| 想定される利用シーン | 必要な容量(目安) | 主なバックアップ対象 |
|---|---|---|
| 家庭(冷蔵庫・照明・スマホ充電) | 1,000〜2,000Wh | 冷蔵庫、LED照明、スマートフォン |
| 個人事務所(PC・ルーター・プリンタ) | 500〜1,500Wh | デスクトップPC、Wi-Fiルーター、プリンタ |
| 医療機器(在宅酸素・吸引器) | 2,000〜4,000Wh | 酸素濃縮器、吸引器、その他医療機器 |
| 災害時の拠点(防災無線・通信) | 3,000Wh以上 | 衛星電話、防災無線、防災用LED灯 |
設置場所の選定と安全対策
バックアップ電源の設置箇所は、安全性・利便性・メンテナンス性を考慮して選びましょう。特に家庭用蓄電池やポータブル電源は、直射日光や高温多湿を避け、安定した床面に設置する必要があります。マンションやアパートの場合、共用部設置の許可や消防法など法令の確認も必須です。発電機の場合は、屋外で排気ガスが籠もらない場所に設置し、一酸化炭素中毒や火災リスクへの十分な対策が求められます。UPS(無停電電源装置)は、アクセスしやすく熱がこもらない場所に配置してください。
また、防災観点からは非常時にもすぐ取り出せて使用できる動線の確保が欠かせません。大型機器の場合、動かせない据え付けタイプかどうか、電源工事が必要かなども事前にチェックしましょう。
維持・管理の方法と重要性
バックアップ電源は、「導入して終わり」ではありません。定期的な維持管理と動作確認が不可欠です。例えば蓄電池の場合、バッテリーの自然放電や劣化を防ぐための定期充電・点検が必要です。またUPSは、バッテリー交換時期が製造から3〜5年程度とされており、定められた交換サイクルを守らないと、停電時に正常に作動しないリスクがあります。
発電機の場合、ガソリンや軽油などの燃料備蓄管理と、エンジンオイル・フィルターの定期交換、始動テストなどのメンテナンスも重要です。特に、災害時すぐに使える状態を保つためには、説明書に従った自主点検と必要に応じた業者メンテナンスを実施してください。
そして、いざという時に「充電切れ」「劣化で使えない」とならないよう、月1回など定期的な動作・充電チェックを習慣化し、不具合時は速やかに専門業者へ相談しましょう。
バックアップ電源のリアルコストとは

機器導入費用の相場
バックアップ電源は、その種類や用途によって導入費用が大きく異なります。家庭向けと業務用、導入予定の用途、必要な電源容量によって費用感は変動しますが、代表的な製品の導入費用相場を下記の表にまとめます。
| バックアップ電源の種類 | 容量の目安 | 導入費用相場 | 主な利用シーン |
|---|---|---|---|
| ポータブル電源 | 300Wh~2,000Wh | 3万円~25万円 | スマホ充電、照明、小型家電 |
| 家庭用蓄電池 | 4kWh~12kWh | 70万円~200万円 | 冷蔵庫やエアコン、生活家電全般 |
| UPS(無停電電源装置) | 500VA~10kVA | 1万円~50万円 | パソコン、サーバ、通信機器 |
| 発電機 | 900W~5kW | 5万円~40万円 | 屋外イベント、緊急時の家電給電 |
家庭用蓄電池の場合、初期費用は高額ですが、停電時の長時間使用や太陽光発電との併用が可能なメリットがあります。一方、ポータブル電源やUPSは手軽に導入できますが、容量や出力に制限があるため、用途を明確にした上での選定が求められます。
初期費用とランニングコスト
バックアップ電源のコストは、機器そのものの購入価格だけでなく設置費用やメンテナンス費用、電気代など継続的なランニングコストが発生します。例えば家庭用蓄電池は施工費が10万円〜30万円程度かかる場合があり、定期的な点検や部品交換も必要です。
UPSの場合はバッテリー部分の寿命が短いため、3年〜5年ごとにバッテリー交換費用(1万円〜10万円前後)が発生します。発電機の場合は燃料(ガソリンやガス)代やオイル交換、運用時の定期点検がコストに加わります。
| 種類 | 主なランニングコスト | 目安額(年間) |
|---|---|---|
| ポータブル電源 | 充電時の電気代、バッテリー交換 | 1,000円~3,000円 |
| 家庭用蓄電池 | 定期点検、バッテリー交換、電気代 | 5,000円~2万円 |
| UPS | バッテリー交換 | 2,000円~1万円 |
| 発電機 | 燃料費、オイル交換、点検費 | 3,000円~1万円 |
導入前に初期費用だけでなく、維持コストや交換サイクルも踏まえて長期的な総コストを試算することが重要です。
補助金や優遇制度の活用方法
日本では、自治体や国の支援策によりバックアップ電源導入時に補助金が受けられる場合があります。特に、家庭用蓄電池や再生可能エネルギー併設システム(例:太陽光発電+蓄電池)を導入する際は、全国的に自治体独自の補助金や「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」補助金制度の対象となる場合もあります。
また、中小企業向けにもBCP(事業継続計画)対策の一環として、中小企業庁による補助制度や防災関連設備導入補助金が活用できることがあります。詳細は各自治体や関連省庁ホームページで確認し、申請期限や必要条件を把握して適切に活用しましょう。
コストパフォーマンスで選ぶおすすめ製品
バックアップ電源の導入においては、コストパフォーマンスの高い製品選定が必要です。以下に、家庭・中小事業所で人気のある導入実績の高い製品を例としてご紹介します。
| 製品名 | タイプ | 容量/出力 | 参考価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Anker PowerHouse II 1500 | ポータブル電源 | 1,424Wh/1,800W | 189,900円 | 大容量・多彩な出力端子・家庭用コンセント可 |
| ニチコン ESS-U2M1 | 家庭用蓄電池 | 11.1kWh | 180万円前後(工事費込) | 長時間稼働・太陽光発電連携 |
| オムロン BY35S | UPS | 350VA/210W | 12,000円前後 | コンパクト・PCやネットワーク機器向け |
| ホンダ EU16i | 発電機 | 1.6kVA | 13万円前後 | 軽量・静音設計・屋外対応 |
自分の利用目的や重視する性能、設置条件、予算に合わせて総合的に比較検討することが、無駄なく安心できる選択に繋がります。
万全な備えで停電に備えるためのステップ
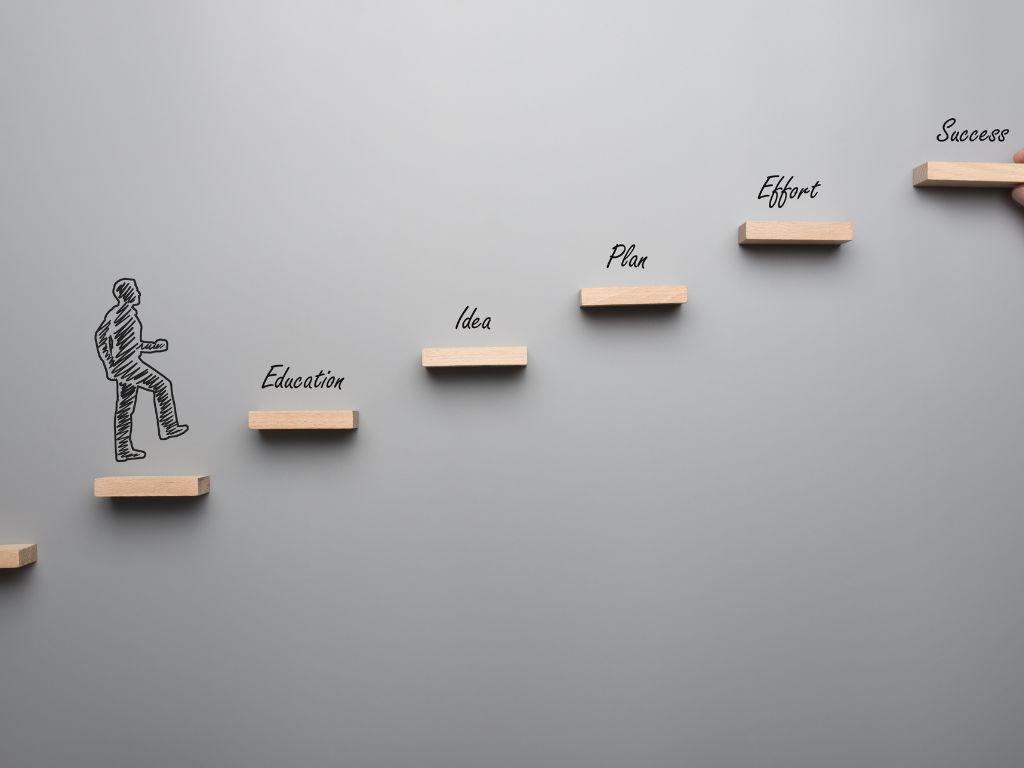
必要性の見極めと相談先
バックアップ電源を導入する前に重要なのは、自宅や事業所について「停電時に本当に必要となる電力の規模」と「非常時に稼働を続けるべき機器」の洗い出しです。例えば、冷蔵庫や照明だけでなく、医療用機器やサーバー、通信機器など、止めることができない機器の一覧と、その消費電力を具体的に調査しましょう。
また、自治体や地域の防災センター、家電量販店、大手の電設施工会社、メーカーの専用相談窓口など、信頼できる相談先にアドバイスを求めることで、最適なバックアップ電源の種類や容量の判断に役立ちます。近年は、太陽光発電システムと蓄電池の組み合わせが推奨されるケースも増えています。
購入から設置、メンテナンスまでの流れ
| ステップ | 主な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 製品選定 | 必要容量・使用機器・利用シーンを踏まえて、ポータブル電源・家庭用蓄電池・UPS・発電機から最適なものを選ぶ | 日本メーカー(パナソニック、シャープ、オムロンなど)の製品は信頼性が高く、アフターサービスも充実 |
| 2. 購入手続き | 電気店やWebショップ、または施工会社を通じて正式に申し込みを行う | 保証内容とサポート体制を必ず確認すること |
| 3. 設置・工事 | 家庭用蓄電池や発電機の場合は専門業者による設置・電気工事が必要 | 見積書の内訳や設置場所の安全性・防災対策も重要 |
| 4. 動作確認 | 設置後、実際に停電時の電源切り替えや自動連携などの挙動を試運転で確認 | 万が一のトラブル時もすぐに相談できる連絡先を把握しておく |
| 5. メンテナンス | 定期的な電池残量チェック・発電機燃料補充・各種部品の点検・交換 | メーカー推奨の点検周期を守り、数年ごとの有料メンテナンスプラン活用も検討 |
メンテナンスを怠ると、いざというときにバックアップ電源が作動しないリスクがあるため、必ず定期点検を行うことが重要です。
さらに、各機器にはメーカーごとに保証期間やサポート内容が異なるため、購入時には信頼のおける国内メーカー品を選ぶことが長期の安心につながります。また、設置後は家族・スタッフ全員が操作手順を理解しておくことで、緊急時の混乱を防ぐことができます。停電に備える体制づくりは、万全なバックアップ電源だけでなく、日常の意識改革・情報共有も鍵を握ります。
まとめ

近年の自然災害増加により、停電リスクは高まっています。家庭用蓄電池やポータブル電源、UPSなどのバックアップ電源を導入することで、停電時も医療機器やIT機器の安心稼働が確保できます。初期費用やランニングコスト、補助金の活用などを考慮し、自宅や事業所に最適な製品を選びましょう。事前の備えこそが被害を最小限に抑えるための最大の防御策となります。