「電気設備の安全管理は大企業だけのもの」と油断していませんか?本記事では、中小企業が見落としやすい「漏電」「老朽化」「過負荷」など3つの電気設備トラブルのリスクと具体的な対策を詳しく解説します。これを読めば、事故や業務停止を未然に防ぐためのポイントがわかります。
中小企業が抱える電気設備管理の現状

中小企業における電気設備の管理状況は、大企業に比べて人的・資金的なリソースが限られていることから、十分な保守点検や計画的な設備更新が行われにくい傾向にあります。経営者や担当者が日常業務に追われてしまい、トラブルが発生して初めて問題に気付くケースも少なくありません。
中小企業における設備管理体制の実情
多くの中小企業では、専門の電気管理技術者を常駐させていない、もしくは社内に電気設備に精通したスタッフが不在という現状があります。そのため「いつ」「どのように」点検や保守を実施すればよいのか分からないまま、日常の管理が後回しになりがちです。また、設備に異常が起きた際も、メーカーや電気工事業者への連絡や対応が遅れるケースが見受けられます。
| 課題 | 主な要因 | 代表的な影響 |
|---|---|---|
| 定期点検の未実施 | 人員・時間不足、知識不足 | 故障・事故の早期発見遅れ |
| 老朽化設備の継続使用 | 予算不足、情報不足 | 漏電・火災のリスク増大 |
| トラブル発生時の対応体制不備 | 業者との連携未整備 | 復旧までの時間・損害拡大 |
よくある誤解とリスクの認識不足
「設置してから問題なく使えているから大丈夫」「毎日の業務で特に異常がないから安心」といった認識を持ちやすいことも大きな問題です。しかし、電気設備の経年劣化や過負荷状態は、表面上の異常がなくても内部では着実に進行するため、目に見えないリスクを長期にわたり放置してしまう危険性があります。
特に、省エネや省コスト経営を重視する傾向が強い中小企業においては、「設備の更新・点検は後回しでも良い」という判断が重大な事故や業務停止に直結しかねないことを再認識する必要があります。
電気設備トラブルがもたらす影響
トラブル発生時には、機器の故障による生産停止、OA機器やパソコンのデータ消失、事務所や店舗の停電による業務停止、さらには火災や感電事故による人的損害など、中小企業経営にとって致命的となるリスクが少なくありません。
また、製造業、物流業、IT企業、サービス業など業種を問わず、「予期せぬ電気トラブル」が顧客信頼の低下や納期遅延、損害賠償請求の対象になるなど、信用面でも大きなマイナスを招く可能性があるため、日ごろからの管理意識と体制づくりが重要です。
見落としがちな電気設備トラブル1 漏電による事故リスク

漏電の兆候と原因
漏電は外見からは気付きにくい隠れたトラブルですが、放置すると深刻な安全事故や経済損失を招く可能性があります。主な兆候としては、分電盤の漏電ブレーカーが頻繁に落ちる、特定の回路で照明やOA機器の動作不良が起きる、電気代の急な増加が見られる、などが挙げられます。
漏電が発生する原因としては、下記のようなものが考えられます。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 配線の絶縁劣化 | 長年の使用によりケーブル被覆が老朽化、絶縁性能が低下する |
| 湿気や水漏れ | 分電盤、コンセント周辺への結露や水気の侵入で導通しやすくなる |
| 設備・機器の故障 | コピー機、エアコン、照明など内部部品の劣化や破損 |
| 施工不良 | 施工時の配線ミスや不適切な設置により本来の回路が損傷 |
感電・火災につながるケース
漏電を放置した場合、重大な事故につながるリスクが高まります。例えば、漏電した電線や設備に触れたことによる感電事故、絶縁不良部分から発熱・発火し、オフィスや工場の火災が発生した例も多数報告されています。
特に日本の梅雨や台風シーズンなど湿度が高い環境では、漏電による感電や火災リスクが増加します。厚生労働省や総務省の消防庁も、事業所での年度別の電気火災発生件数の増加に警鐘を鳴らしています。
| 主な被害 | 発生事例 |
|---|---|
| 感電事故 | 床の水たまりに漏電したコードが触れ、作業員が感電 |
| 部分火災 | 倉庫内の古い電力量計の絶縁不良から発火、在庫品焼失 |
| 経済的損失 | 製造ラインの電気設備が短絡、長時間停電で納期遅延 |
定期点検の重要性
漏電は「いつの間にか進行する」経年劣化や軽微な不具合が原因となるため、日常的な目視点検やプロによる定期点検が極めて重要です。
法令(労働安全衛生法・電気事業法等)では、事業所の電気設備点検が義務付けられていますが、中小企業ではコストや人手不足等の理由から点検が後回しになりがちです。しかし、専門会社による漏電診断(絶縁抵抗測定やサーモグラフィ調査など)を定期的に実施することで、リスクを大幅に低減できます。
また、三菱電機やパナソニックなど国内メーカーが提供する漏電遮断器の設置・交換も有効な対策です。定期点検と機器の適切な更新により、「もしも」に備えることが可能です。
見落としがちな電気設備トラブル2 老朽化した分電盤や配線

多くの中小企業で見落とされがちな電気設備トラブルのひとつが「老朽化した分電盤や配線」の放置です。分電盤や配線は、建物の心臓部ともいえる重要設備でありながら、一度設置すると長期間意識されることが少なく、経年による劣化や寿命超過がしばしば見過ごされています。これらの不備は、定期的な点検や更新を怠ることで、思わぬ事故やトラブルの引き金となります。
分電盤・配線の寿命と交換時期
日本国内の電気設備基準に則ると、分電盤や屋内配線の法定耐用年数はおおむね10~20年とされています。特に、1980年代以前に設置されたものや、経年でメンテナンス履歴の不明な分電盤・配線は、「絶縁性能の低下」や「端子の緩み・腐食」による劣化リスクが高まっています。製品の性能や設置環境によって前後しますが、主要メーカー(例:パナソニック、河村電器産業、三菱電機など)は、15年~20年を目安に交換を推奨しています。
| 設備名 | 耐用年数(目安) | 主な劣化症状 |
|---|---|---|
| 分電盤 | 15~20年 | 腐食・変色・異音・焦げ臭さ |
| 屋内配線(ビニール絶縁電線等) | 20~30年 | 絶縁被覆のひび割れ・変色・硬化 |
| ブレーカー・漏電遮断器 | 10~15年 | 動作不良・トリップ不可 |
老朽化による停電・誤作動のリスク
老朽化した分電盤や配線は、導通不良や短絡、烏よけカバーの損傷による被害など、多岐にわたるリスクを孕んでいます。配線内での絶縁破壊が起きれば、予期せぬ「停電」や「誤作動」が発生し、業務の停止やOA機器の損傷を招くだけでなく、漏電火災や感電といった重大事故に発展する可能性も高まります。特に、古い分電盤内でのホコリ蓄積や湿気による腐食は、通電時の発熱やスパークの大きな要因です。
また、現代型のOA機器や高効率照明、エアコン等を旧来の配線でまかなおうとすると「電圧降下」「発熱」も生じやすくなります。点検記録が残っていない、あるいは設置後20年以上経過したままの場合は、トラブルの前兆を見逃さないよう早めの対応が肝心です。
交換・更新のタイミングと目安
分電盤や配線の交換・更新は、「年数の経過」と「劣化症状の有無」両方から判断するのが鉄則です。目視で分電盤内部の部品サビ・焦げ跡・異音の有無を確認し、次の表の目安を参考にしましょう。
| 判断基準 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 設置後20年以上経過 | プロによる総合診断・計画的な交換 |
| 異臭・焦げ・異音の発生 | ただちに専門業者に点検依頼、必要なら即時交換 |
| 増設・改修時に配線の劣化判明 | 改修時に合わせて配線・分電盤の更新 |
また近年では、雷サージ保護機能付き分電盤や、IoT連動で遠隔監視可能なスマート分電盤も普及しつつあります。これらへの切り替えは、トラブル予防とともに省エネ・BCP対策の面でも企業価値向上に寄与します。
電気主任技術者または機械設備に詳しい専門業者の定期診断と的確なアドバイスを受け、タイミングを逃さずリスクを低減することが重要です。
見落としがちな電気設備トラブル3 エアコンやOA機器の過負荷運転

オフィスや店舗など、中小企業の現場ではエアコンやパソコン、コピー機、プリンターなどのOA機器を同時に稼働させる機会が増えています。しかし、これらの機器の負荷を正しく把握せずに使用を続けると、回路に過剰な電流が流れ、思わぬトラブルにつながることがあります。ここでは、過負荷運転による具体的なリスクとその対策について解説します。
機器の同時使用によるブレーカー落ち
多くの中小企業では、限られた回路に複数の電気機器を集中して接続しているケースが多いです。たとえば、夏場のピーク時にエアコンやサーバー、OA機器を一斉に使うことで、一回路あたりの設計容量を簡単に超えてしまうことがあります。その結果、「ブレーカーが突然落ちて業務が中断した」「重要なデータが消失した」などの被害が発生しています。
機器ごとの消費電力やブレーカーの容量は必ず確認し、計画的な配線や負荷の分散を心がける必要があります。
過負荷による発熱・火災事故
過負荷状態が継続すると、コンセントや配線の発熱、さらには機器内部の部品劣化が進みます。国内でも、コンセントや延長コードが発熱・発煙し、火災に発展する事故が毎年発生しています。OAタップ1つで複数の機器を同時に使用していると、どのくらいの電力が流れているのか分からず、危険性が高まります。目に見えない配線やコンセント部分にも注意が必要です。
| 主な電気機器 | 概算消費電力(W) | 主な発熱・火災リスク要因 |
|---|---|---|
| エアコン(業務用) | 1500~2500 | 長時間連続運転、内部の埃、設計容量超過 |
| パソコン(デスクトップ) | 100~300 | OAタップ過負荷、古い配線の劣化 |
| レーザープリンター | 300~1500 | 立ち上げ時の瞬間高負荷、延長コードの劣化 |
| 電子レンジ | 1000~1500 | 専用回路でない場合の容量超過 |
特に夏季や冬季は、瞬間的な消費電力が一気に上昇するため、既設の配線や分電盤の能力との適合性を見直すことが重要です。
電力契約容量の見直し・節電対策
「すぐブレーカーが落ちる」「電気代が予想以上に高い」と感じたときは、電力契約容量と実際の消費電力のバランスに問題がある可能性があります。契約容量が小さすぎると、ブレーカーの頻繁な遮断や業務への支障が発生します。反対に十分すぎる容量を設定していると、基本料金の無駄な上昇を招きます。
以下のような対策が有効です。
| 推奨対策 | ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 設備ごとの消費電力の「見える化」 | 分電盤にワットチェッカー等を設置 | 無駄な電力消費・過負荷の箇所の特定 |
| 契約容量の最適化 | 電力会社・電気工事業者に相談し適正値へ | コスト削減とブレーカー遮断リスクの低減 |
| OAタップや配線の増設・分散 | 回路ごとの負荷分散、専用回路の追加 | 一箇所への集中負荷・発熱リスクの回避 |
また、省エネ型の機器へ買い替えることで、日常的な電力使用量の削減と電気事故の防止を両立できます。
電気設備のトラブルを未然に防ぐためのポイント

プロによる定期診断の必要性
電気設備トラブルを回避するためには、電気工事士や専門の保守会社による定期的な診断・点検が不可欠です。 特に漏電や老朽化、配線の損傷は、見た目だけでは発見しにくい問題が多く、プロの知見と専用機器による調査が欠かせません。 こうした定期診断を実施することで、トラブル発生前の早期発見・予防保全につなげることができます。 また、法律で義務付けられている「定期自主検査」や「年次点検」も積極的に行い、管理記録を残すことが重要です。
| 主な点検項目 | 推奨頻度 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 分電盤・配電盤 | 年1回以上 | 端子や接点の緩み・腐食、動作確認 |
| 漏電ブレーカー | 半年に1回 | 動作テスト、絶縁抵抗測定 |
| 照明・コンセント回路 | 年1回 | 配線・プラグの損傷、過熱・異臭の有無 |
社員への基本的な電気安全教育
事業所で働く社員一人ひとりの電気事故防止意識を高めるため、定期的な安全教育がとても重要です。 具体的には、漏電・火災・感電時の対応方法や、異常時の電源遮断手順、日常点検のポイントなどをマニュアル化し、社内研修や朝礼などで周知徹底しましょう。 また、エアコン・OA機器等の電気機器の正しい使用法や、過負荷の見分け方に関する教育も不可欠です。
| 教育内容 | 頻度 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 電気事故時の初動対応 | 年1回 | 実技訓練・マニュアル配布 |
| 日常点検のチェック方法 | 半年に1回 | 社内講習・ポスター掲示 |
| 正しい電気機器の使い方 | 随時(新規導入時) | 製品ごとの手順説明・質問受付 |
緊急時の対応体制と連絡先の確認
万が一、漏電や火災・感電事故などが発生した際にすぐ適切な対応ができるよう、緊急時の対応マニュアルと、関連する連絡先リストの整備が急務です。 特に、東京電力・関西電力など地域の電力会社、緊急対応が可能な電気工事業者、消防署、ビル管理会社など、状況に応じた連絡先を事前に共有・掲示しておくことが重要です。 また、代表者や管理責任者が不在時にも対応できるよう、複数名での情報共有・訓練を日頃から実施しましょう。
| 想定トラブル | 優先連絡先 | 必要な対応例 |
|---|---|---|
| 漏電・感電事故 | 電気工事業者、119番 | 電源遮断・救急対応・現場保全 |
| 電気設備の火災 | 消防署・電力会社 | 避難誘導・消火・関係機関への通報 |
| 停電・機器の故障 | 電力会社・ビル管理会社 | 復電対応・機器点検・再発防止策の検討 |
まとめ
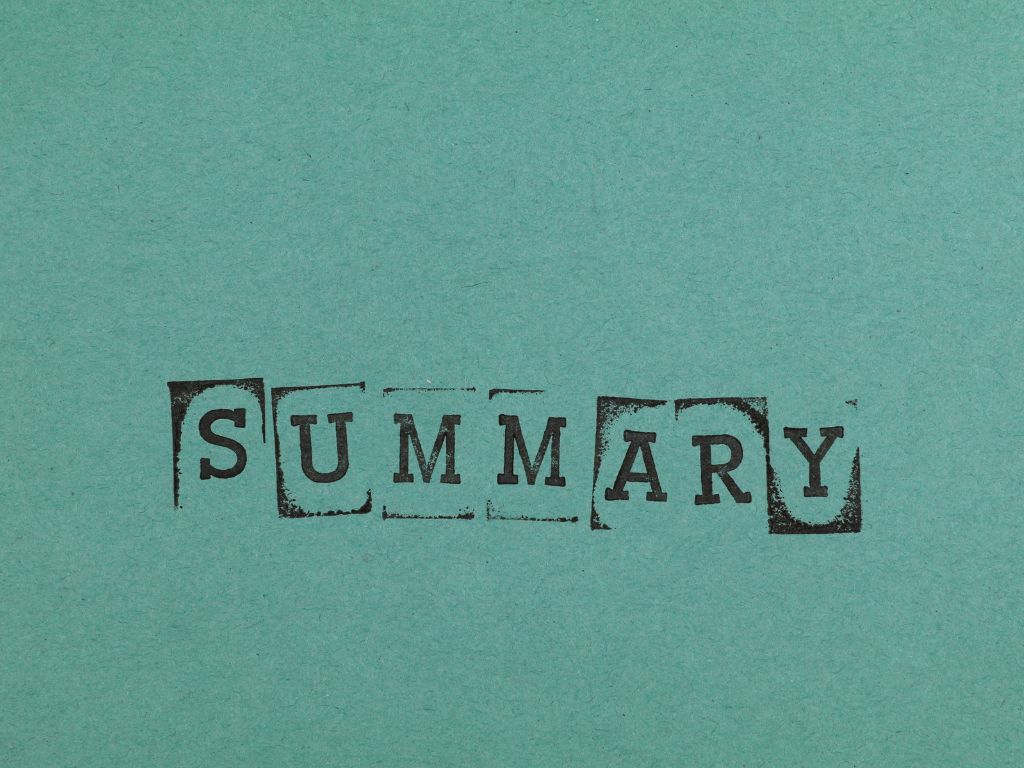
中小企業が見落としやすい電気設備トラブルには、漏電、老朽化した分電盤や配線、エアコン・OA機器の過負荷運転が挙げられます。これらは火災や停電など重大事故の原因となるため、定期点検や適切なメンテナンス、社員への電気安全教育が不可欠です。東京電力やパナソニックなど信頼できる業者による診断を活用し、安心・安全な職場環境を維持しましょう。