節電は中小企業経営において重要ですが、やり方を間違えるとコスト増や業務効率の低下、社員の不満につながる“逆効果”となる場合があります。本記事では、正しい節電の知識と実践方法、よくある失敗例、その対応策や実践的な節電アイデアまでを分かりやすく解説し、経営にプラスとなる節電の進め方を導き出します。
中小企業が節電を意識する理由

中小企業が節電を意識する理由は、単純なコスト削減だけでなく、経営の安定や社会的責任、そして従業員の働く環境向上まで多岐にわたります。昨今、電気料金の高騰や慢性的な電力需給の逼迫が続いており、エネルギーコストの増加は経営に直結する重大な課題です。特に、製造業やサービス業を中心とした中小企業では、利益率が限られる中でのコスト上昇が経営を圧迫しやすい現状があります。
また、省エネルギーや節電への取り組みは、社会的な責任という側面も意識されています。SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの流れのなかで、事業活動を通じて省エネ・節電に取り組むことが、企業価値の向上や取引先からの信頼獲得につながっています。
加えて、従業員の快適な職場環境維持も、安易に無理な節電をすれば作業効率や安全性の低下を招きかねず、適切な方法でエネルギー使用を最適化することが求められています。
| 背景 | 理由詳細 | 具体例 |
|---|---|---|
| 経営面 | 電気料金高騰による収益悪化の抑制 | 空調や照明などの光熱費削減 |
| 社会的責任 | 環境配慮やSDGsへの貢献による企業価値向上 | 省エネ活動の情報発信やCSR報告 |
| 従業員満足 | 快適かつ安全な職場環境の確保 | 無理のない範囲での空調設定や節電ルール |
| 災害・停電対策 | 非常時の備えや事業継続計画(BCP)の一環 | 節電の習慣化によるリスク分散 |
これらの理由から、多くの中小企業が経費削減や企業の持続的成長、信頼性の向上を実現するために積極的に節電に取り組む必要性を認識しています。単なる「経費減」だけでなく、経営戦略の一環として節電を捉えることが重要です。
節電の基本知識とよくある誤解
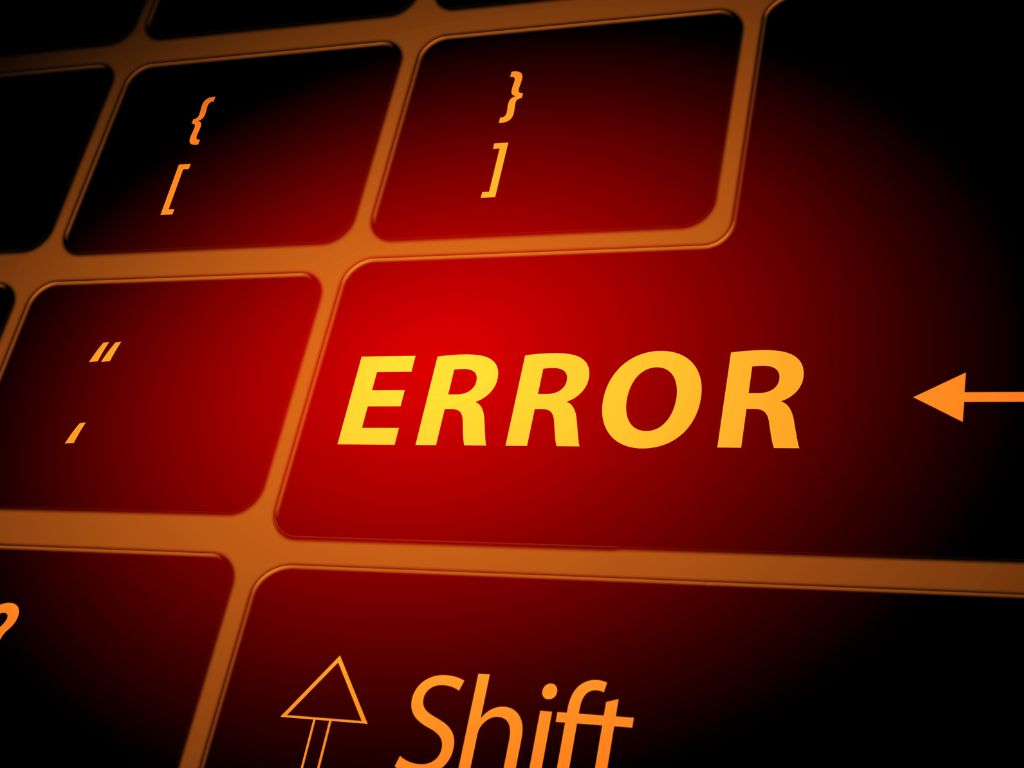
節電を実践する前に、まずその基本的な考え方や正しい知識を理解することが重要です。ここでは節電と省エネの違いを明確にし、多くの中小企業で見られるよくある節電の誤解について解説します。
節電と省エネの違い
多くの人が混同しがちですが、「節電」と「省エネ」は似て非なるものです。節電は〈単純に電力消費を抑えること〉を指し、省エネは〈機器の効率化や運用の工夫によってエネルギー全体を無駄なく使うこと〉を意味します。
| 項目 | 節電 | 省エネ |
|---|---|---|
| 定義 | 電気の使用量そのものを削減 | エネルギーの効率的活用で無駄を減らす |
| 方法 | 使用時間の短縮や電源オフ | 高効率機器の導入・運用改善 |
| 例 | 照明器具の消灯 エアコンの稼働を減らす | LED照明の導入 インバータエアコンへの切替 |
単なる消費電力の削減が必ずしも企業経営における「コスト削減」や「生産性向上」に結びつくわけではなく、運用の工夫と効率化が重要です。
間違いやすい節電方法の例
一見効果的に思えても、実は逆効果または意味がない節電方法を選んでしまうケースが目立ちます。その代表例を以下にまとめます。
| 誤った節電方法 | 主な問題点 |
|---|---|
| エアコンを頻繁にオン・オフする | 起動時の消費電力が高まり、かえって電気料金が増加 |
| 窓を開けて空調を使う | 空調効率が著しく低下し、設定温度に達しにくくなる |
| 全ての照明を一斉消灯 | 作業環境が悪化し、生産性や安全性の低下につながる |
| パソコンや複合機の主電源断 | 再起動やトラブル発生で業務効率悪化・故障リスク増 |
| 電力ピーク時だけの節電 | 電力契約料金の根本的な削減には結びつきにくい |
これらの例からも明らかなように、やみくもな節電は効果が薄く、場合によっては従業員の健康リスクや企業ブランドの低下につながることもあるため、冷静な判断と基礎知識が求められます。
身近な対策ほど「なぜこの方法が効果的なのか」を理解し、納得のいく節電を進めていくことが、中小企業の電気料金対策やSDGs推進の観点からも不可欠です。
やり方を間違えると逆効果になる節電の具体例
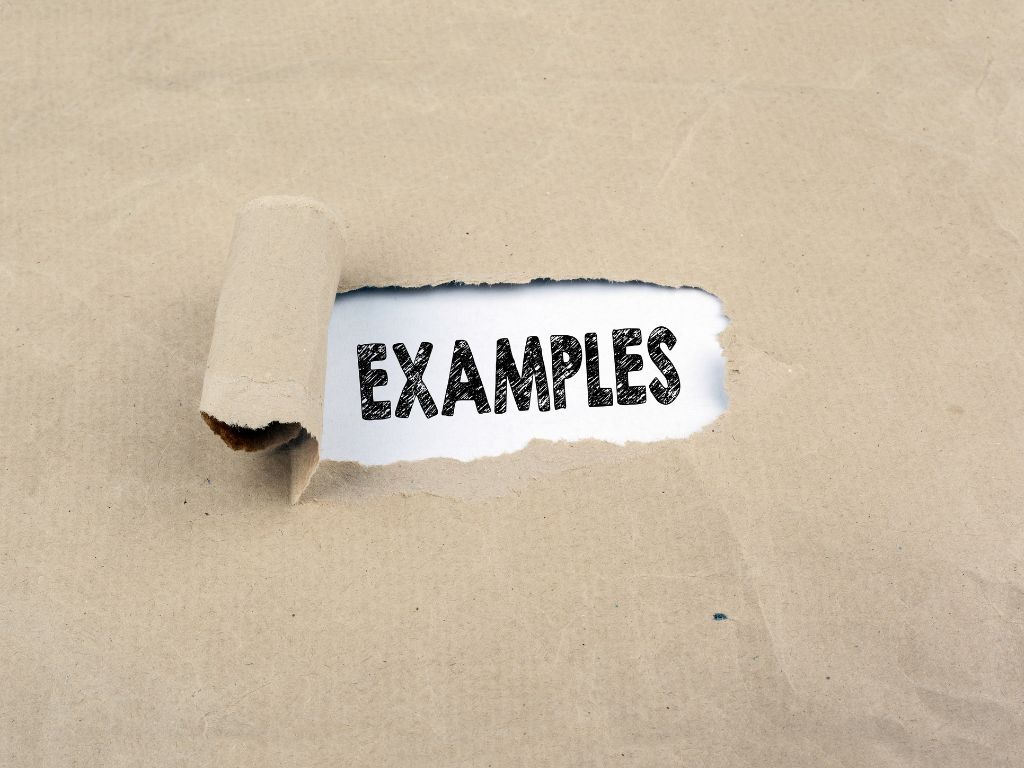
節電はコスト削減や環境配慮のため重要ですが、その方法を誤ると期待した効果が得られないばかりか、業務効率の低下や想定外のコスト増加を招く場合があります。ここでは中小企業で実際に起きがちな、逆効果となる節電の具体例について詳しく解説します。
エアコンの使い方を間違えた場合の落とし穴
真夏や真冬のオフィスでのエアコン利用は、電気代の大きなウェイトを占めます。しかし、温度設定や運用方法を過度に厳しくすることは逆効果につながります。例えば「夏は28度以上、冬は18度以下」に強制すると、室内が不快になり、集中力や作業効率が落ちます。その結果、従業員が個別に扇風機や電気ヒーターを持ち込むなど、かえって消費電力が増えてしまうケースもあります。
| 節電行動 | 想定される効果 | 逆効果の例 |
|---|---|---|
| 設定温度を過度に高・低くする | 冷暖房費の削減 | 業務効率低下、個別ヒーターや扇風機の使用増加 |
| 頻繁な電源ON/OFF | 稼働時間の短縮 | 立ち上がり時に電力を多く消費し、トータル消費電力が増加 |
パソコン・OA機器の電源管理の誤り
「業務時間外は全てのパソコン・OA機器の主電源を完全にOFFにする」といった画一的なルールは、実は注意が必要です。例えば、システムの自動アップデートやバックアップ作業が夜間に設定されている場合、これらが完了せずトラブルを誘発します。また、頻繁なシャットダウン・電源ONは機器自体の寿命を縮める原因にもなります。
| 節電として指示された行動 | そのメリット | 実際に起きたデメリット |
|---|---|---|
| パソコンの主電源を毎日完全OFF | 待機電力カット | アップデートやバックアップの失敗による情報漏洩・システムトラブル |
| プリンタや複合機の主電源OFF | 無駄な待機電力の削減 | 起動時に時間や電気を消費、作業の遅延 |
節電設定による業務効率低下やコスト増加
「省エネモード」や「自動スリープ」「消灯時間の短縮設定」などの導入は一見正しい節電ですが、業務プロセス全体を考えずに導入すると弊害が出ます。例えば、照明の自動消灯時間を極端に短くした結果、頻繁な点灯・消灯により電球の寿命が縮まったり、作業中にいきなり消灯して作業が中断されたりするケースがあります。また、複数回に分けてコピーや印刷を行ったり、機器の起動・停止が多くなったりすると、合計の電力使用量が増すこともあります。
- 業務プロセス全体の見直しなしに節電設定のみを厳しくすることは推奨できません。
- 結果として「節約できていない」「働きやすさが損なわれて離職率が上がる」などの副作用を招きます。
正しい節電の考え方と成功例

中小企業が節電に成功するためには、「ただ単に電気を使わない」ことをゴールとせず、快適さ・業務効率・コスト削減をバランスよく実現する視点が必要です。ここでは、無理や我慢に頼るのではなく、効果的に電力消費を抑えながら企業活動を円滑に進めるための実践的なアプローチとその成功例をご紹介します。
快適さとコスト削減を両立させる工夫
節電だからといって空調を切る、照明を極端に減らすといった方法は、従業員の健康や働きやすさに悪影響を及ぼしかねません。照明をすべてLED化することで明るさはそのままに電気代を削減できたり、エアコンの設定温度を夏28℃・冬20℃にすることで適度な快適さと節電を両立できます。
また、ブラインドや遮熱フィルムの活用によって外気温の影響を最小限にし、冷暖房効率を高めれば、日常的に消費電力量を低減できます。
| 工夫の内容 | 期待できる効果 | 備考 |
|---|---|---|
| LED照明の導入 | 消費電力約1/2、長寿命化 | 初期費用は補助金活用も可能 |
| 空調の適正設定 | 無理のない消費電力削減 | 社員の意見を聞き温度設定 |
| 遮熱フィルムやブラインド | 冷房・暖房効率向上 | 小規模投資で大きな効果 |
社員の意識改革と社内ルール作り
節電の成功は、社員一人ひとりの意識改革が不可欠です。トップダウンで節電目標を定めるだけでなく、社員を巻き込んでアイデアを募り、「帰社時のパソコン・照明完全オフ徹底」や「コピー機・プリンターの省エネモード利用促進」など、日常に定着しやすいルールを明文化しましょう。
実際に、社内で“節電チーム”を立ち上げ、定期的に進捗や新たなアイデアを共有することで、継続的に成果を上げている企業の事例もあります。加えて、「目に見える形で消費電力量を掲示する」ことで社員のやる気アップにつながります。
電気料金プランや補助金活用など経営目線からのアプローチ
電気料金プランの見直しもコスト削減の大きなカギです。「時間帯別電力量契約」へ切り替え、昼間の業務をシフトするなど、企業の稼働実態に適したプラン選定が不可欠です。国や自治体の補助金・助成制度を活用し、省エネ設備投資の初期負担を軽減した事例も多く見られます。
以下に、中小企業が実際に活用した支援制度や料金プラン見直し事例を挙げます。
| 実施内容 | 活用できる制度・プラン | 成果 |
|---|---|---|
| 省エネ照明へのリプレイス | 経済産業省エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | 投資初年度で最大30%電気使用量削減 |
| 電気契約プラン見直し | 東京電力「スマートライフS」など時間帯別プラン | 業務の時間ずらしにより年間10万円以上コストダウン |
| 空調更新による高効率化 | 東京都中小企業向け省エネ設備導入助成 | 脱フロン・省エネで次年度も補助継続利用 |
このように、正しい節電は、「工夫」と「社員参加」、「賢い経営判断」の三位一体で、大きな成果をもたらします。コスト削減や省エネだけでなく、働きやすさや会社のイメージ向上にもつながる点が現代の中小企業にとって最も重要なポイントです。
中小企業でよくある節電失敗事例
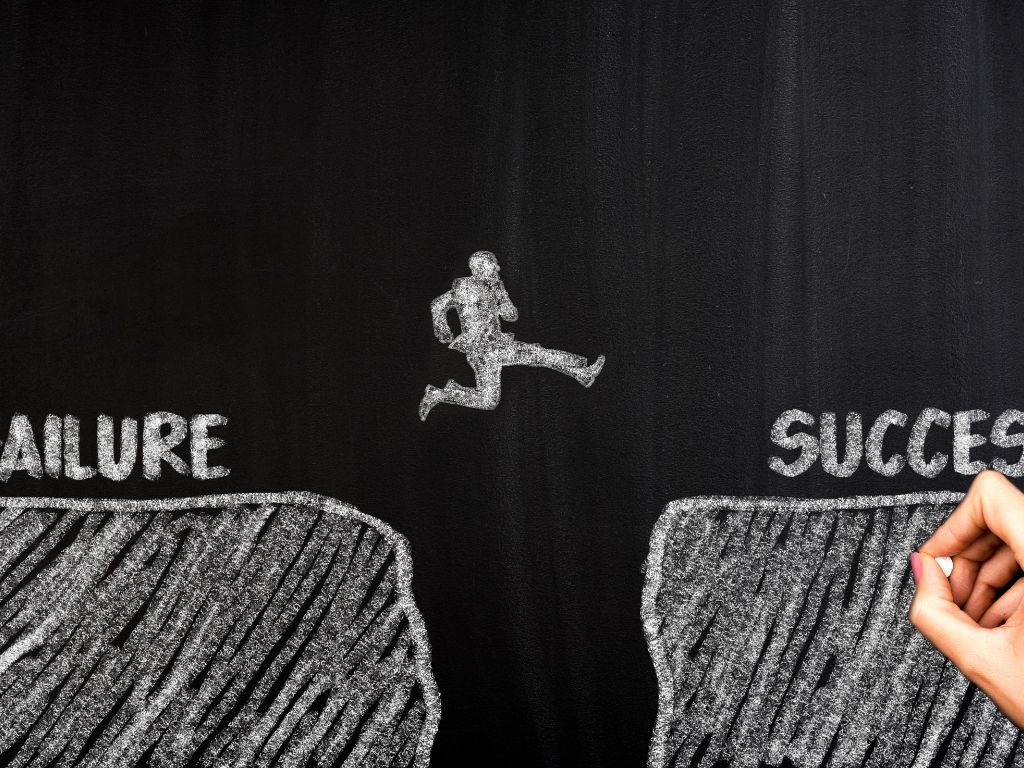
ありがちな落とし穴とその対応策
中小企業が節電に取り組む際、善意から始めた行動が思わぬ失敗や逆効果を引き起こすことがあります。ここでは、よくある具体的な失敗事例を挙げ、その原因と対応策を整理します。
| 失敗事例 | 発生しやすい理由 | よく見られる影響 | 現実的な対応策 |
|---|---|---|---|
| エアコンの一斉オフ | 電気代削減の即効性を期待し、終日空調を止める | 室温上昇による社員の体調不良/機器の不具合 | ピーク時のみ温度設定を調整し、コアタイムやエリアごとに最適な運転を実施 |
| パソコン・OA機器の電源頻繁ON/OFF | 待機電力を嫌い、昼休みや小休憩ごとに全台電源オフ | 機器の寿命短縮/起動時の消費電力増大 | スリープ・省電力モード設定により無理のない消費電力抑制へ移行 |
| 照明の一部だけ消灯 | こまめな消灯がもっとも節電効果が高いと誤認 | 室内の明暗差が大きく、作業効率低下や事故リスク増加 | LED照明化+適切な位置・明るさ確保による安全性向上と省エネ両立 |
| 節電への過度なプレッシャー | 経営者・管理職から従業員への強い節電指示 | 職場の雰囲気悪化/従業員のパフォーマンス低下 | 社員の声を吸い上げ、合意形成型の運用ルール策定に切り替え |
| 省エネ設備の“ただ買い” | 国や自治体の補助金が使えるからと、十分な検証なく設備投資 | 期待したほどの電気料金削減効果が得られない | 本当に必要な場所・規模・機種選定のため、専門家による現地診断を活用 |
ケース別:失敗から学ぶ現場の声
例えば東京都内の印刷会社では、「夏場は全館エアコン設定を28度固定」と決めたところ、倉庫や一部オフィスではかえって室温が30度を超え、作業効率が大きく落ちてしまいました。そこで、エリアごとに冷房温度の運用ルールを見直し、扇風機や遮熱フィルムを併用することで快適性とコスト削減の両立に成功しました。
また、ある製造業では照明の”交互消灯”が影響し、手元が暗くなったことで従業員が工具でケガをする事故が発生。安全衛生の観点からも、過度な節電は本末転倒であると認識されました。
中小企業が陥りやすい節電失敗のポイント
- 短期的な「電気代削減」だけにフォーカスしてしまう
- オフィスや工場の特性・業種・作業内容を無視した一律の対応
- 従業員の体調や安全を犠牲にした節電策
- 設備投資や補助金活用の目的・費用対効果の検証不足
正しい節電は「快適性」「安全性」「業務効率」など総合的な視点でプランニングすることが重要です。失敗事例を他山の石として、自社に合ったアプローチを探る意識が求められます。
中小企業が取り組みやすい実践的な節電アイデア

中小企業が無理なく、かつ即効性のある節電を目指すには、設備投資を抑えた運用改善や、費用対効果の高い方法を選ぶことが重要です。ここでは、実際に多くの企業が取り組んで成功している具体的なアイデアを中心に紹介します。
設備投資不要でできる節電
大掛かりな設備改修をせずに実行できる節電対策は、コスト負担が少なくすぐに取り組めます。日常業務に取り入れやすいものを抽出しました。
| 取り組み例 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 照明の徹底管理 | 日中は自然光の活用 昼休みや不使用エリアでの消灯の徹底 | 最大で20%の照明電力削減 |
| エアコンの設定温度最適化 | 冷房は28℃、暖房は20℃を目安に設定 オフィスのレイアウト工夫で効率向上 | 空調電力の5~10%削減 従業員の体調維持にも配慮 |
| 待機電力のカット | PCや複合機などのOA機器は終業時に主電源オフ 長時間使わない機器はコンセントから抜く | 全体消費電力の約6~10%削減 |
| タイマー・省エネモード活用 | エアコン・照明機器・パソコンの自動オフ設定 | 無駄な稼働時間を防ぎ省電力化 |
| 業務時間のシフト調整 | 夏季は早出・早帰りを検討し、ピーク時間の電力使用を削減 | デマンド料金低減や契約電力の見直しが可能に |
費用対効果の高い取り組み
省エネ補助金や自治体の助成金活用などを利用し、初期コストを抑えて実施できる対策も中小企業に推奨されています。投資回収が比較的短期間で見込める方法を紹介します。
| 対策 | 初期コスト目安 | 運用・効果 |
|---|---|---|
| LED照明への切替 | 従来の蛍光灯比でやや高額 (1本数千円~) | 消費電力量50%以上カット 長寿命・廃棄コスト削減 |
| スマートコンセント・エネルギーマネジメントシステム導入 | 数千円~数万円から導入可能 | 見える化で使用状況を全員が把握 無駄な消費を可視化し削減 |
| 古いOA機器の最新省エネ型への入替 | 機器ごとに数万円~ | 消費電力が20~40%減少 効率化と業務生産性にも寄与 |
| 空調の定期点検・省エネフィルター導入 | 点検:1万円程度~ フィルター:数千円/台~ | 冷暖房効率向上 エアコン消費電力を抑制 |
| ブラインド・窓用断熱フィルムの活用 | 数千円~数万円で導入可能 | 直射日光や外気の影響軽減 冷暖房の設定温度の維持に寄与 |
また、政府や各自治体が実施する「中小企業向け省エネ補助金」や、「東京都 中小企業省エネルギー総合支援事業」などの活用もおすすめです。該当する制度を調べて賢く活用することで、設備投資にかかるコストの大半を補助してもらえるケースもあります。
社内での情報共有と小さな改善の積み重ねが大切です。毎月の電気料金を社員で確認し、具体的な成果を数値でフィードバックすることで、さらなる節電意識の定着に役立ちます。無理なく継続できる仕組み作りを心がけましょう。
まとめ

節電は中小企業にとって重要な経営課題ですが、やり方を間違えると逆効果となり、業務効率やコストに悪影響を及ぼしかねません。正しい知識と対策、また「快適さ」と「コスト削減」の両立を意識した取り組みが、持続的な成果と会社の成長につながります。三菱電機やパナソニックの省エネ機器、国の補助金制度の活用も検討しましょう。