電気設備点検は、建物の安全性と安定した電源供給を確保するために欠かせない作業です。この記事では、初心者にも分かりやすく、電気設備点検の目的、点検項目、法律上のルール、安全対策、実施頻度、チェックリスト、外部委託のポイントまでを網羅的に解説します。これを読むことで、点検の基礎知識から実務に役立つ情報までを体系的に理解でき、安心・安全な電気設備の維持管理が可能になります。
電気設備点検とは何かを初心者にもわかりやすく解説
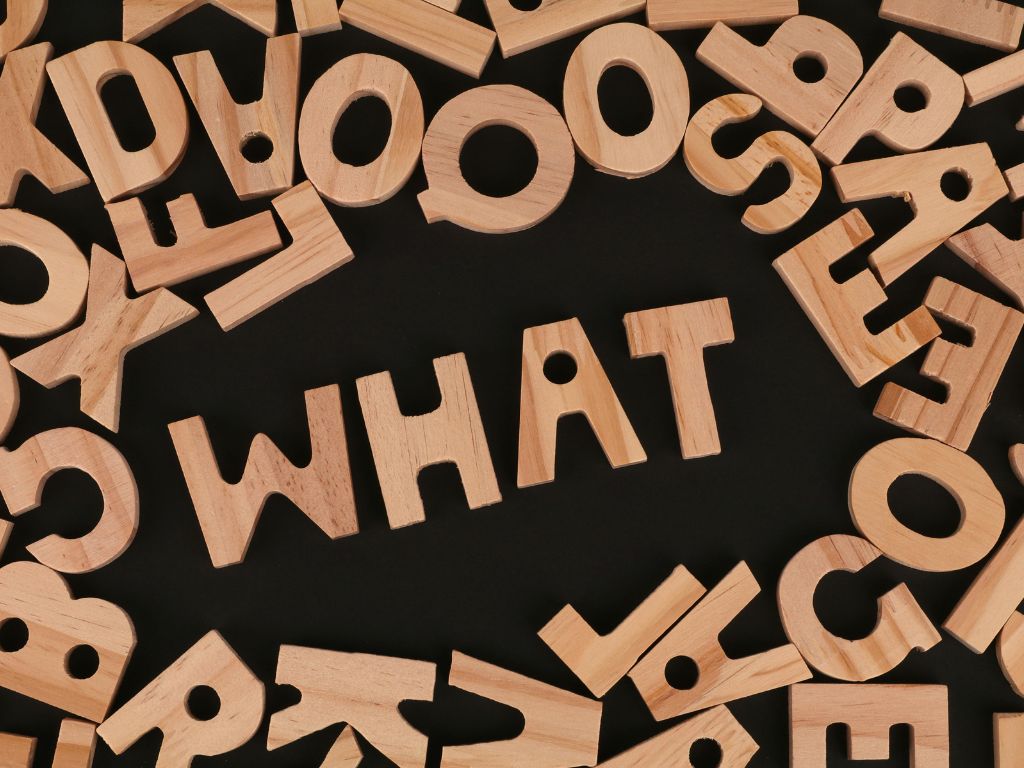
電気設備点検の目的と重要性
電気設備点検とは、建物や施設に設置されている様々な電気設備が、安全かつ適切に機能しているかを定期的に確認する作業です。多くの電気設備は長期間にわたり使用されるため、劣化や損傷が進行すると火災や感電などの重大な事故を引き起こすリスクがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、日常的な点検や定期的なメンテナンスは欠かせません。
また、近年では持続可能なエネルギー活用やBCP(事業継続計画)におけるリスク管理の観点からも、電気設備の健全性確保が重要視されています。企業や公共施設にとっては、電気設備の不具合による業務停止は大きな損失となるため、点検の実施は事業運営の安定化にも寄与します。
法律や基準に基づく点検の概要
電気設備点検は、単なる「自主的な安全確認」だけではなく、法令に基づき実施が義務付けられている場合もあります。日本では主に以下の法律や関連基準に基づいて点検が行われます:
| 法律・指針名 | 主な内容 | 対象設備 |
|---|---|---|
| 電気事業法 | 高圧受電設備など事業用電気工作物の保安確保 | 受変電設備、自家発電設備など |
| 労働安全衛生法 | 労働者の感電・火災防止、保護具の使用基準など | 電動機、電灯設備、コンセント等 |
| 消防法 | 火災予防・火災報知設備や非常電源の点検義務 | 非常照明、非常用発電、避雷設備など |
これらの法令に違反した場合、是正勧告や罰則対象となることもあるため、事業者は定期的な点検を実施し、その記録をしっかり保管する義務があります。
電気事業法と自主点検の違い
電気設備点検には、「法定点検」と「自主点検」があり、それぞれ目的や実施内容に違いがあります。法定点検は主に電気事業法や労働安全衛生法に基づいており、資格を持った電気主任技術者のもとで行われる必要があります。たとえば、高圧受電設備を所有している場合、電気主任技術者の選任が義務です。
一方で、自主点検は法的義務ではないものの、日常的な設備状態の把握や、劣化の早期発見を目的として行うもので、設備管理者や施設管理者によって運用されており、建物の安全性と運用効率向上のために広く実施されています。
以下に、法定点検と自主点検の違いをまとめた表を示します。
| 区分 | 実施根拠 | 対象者 | 主な目的 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 法定点検 | 電気事業法・労働安全衛生法 など | 電気主任技術者 | 法令遵守と設備の安全確保 | 1~2年に1回以上(設備により異なる) |
| 自主点検 | 社内ルールやガイドライン | 施設管理者や技術担当 | 早期異常発見と能動的な保守 | 月1回、週1回など任意で設定 |
このように、点検の分類や実施体制を理解することで、より適切なメンテナンス体制の構築が可能になります。初心者でもまずはルールを押さえることが、安全で信頼性の高い電気設備管理の第一歩となります。
点検の対象となる主な電気設備とその役割

受変電設備(高圧・低圧設備)
受変電設備は、電力会社から供給される高圧の電力を建物内で使用できる低圧に変換するための重要な設備です。主に高圧受電設備、変圧器、遮断器、配電盤などが含まれます。これらの機器は建物全体の電力供給を担う基幹的な役割を持っており、不具合が発生すると大規模な停電や火災の原因になる可能性があります。
受変電設備の点検では、変圧器の絶縁油の状態確認や遮断器の動作確認、漏電の有無、接続端子の緩み、結露や汚損のチェックなどが行われます。また、電圧や電流の測定を通じて電力の安定供給と設備寿命の最適化をめざします。
電灯・コンセント設備
電灯・コンセント設備は、日常的に使用する電力供給口を通じて電気を各所に分配するための設備です。分電盤、照明器具、コンセント、スイッチ類などが該当します。これらの点検は生活や業務環境の快適性と安全性維持に直結しています。
チェックの際には、コンセントの接触不良や焼損跡、照明器具のランプ切れやチラつき、接地線の有無、絶縁性能の検査などが対象となります。また、ハンドドライヤーやコピー機、パソコンなど過大な電流を要するOA機器との接続状況も確認すべき項目です。
避雷設備と接地システム
落雷による設備被害や火災のリスクを軽減するために設置される避雷設備、および電気回路の安全性を確保するための接地システムも点検の対象となります。これらは間接的な感電防止や雷サージの影響を最小限に抑える役割を果たします。
建物の避雷設備には、避雷針・引下げ導体・接地極が含まれ、定期的に接地抵抗値を測定し、劣化や腐食の有無を確認します。接地システムについても、A種~D種の分類ごとに施工基準が異なるため、対象設備に応じた基準への適合状況を精査する必要があります。
| 設備種別 | 目的 | 点検項目 |
|---|---|---|
| 避雷設備 | 雷サージ対策、構造物や機器の保護 | 避雷針の接続確認、接地抵抗値測定、導体腐食の有無 |
| 接地システム | 感電・火災リスクの低減、安全な漏電経路の確保 | 接地抵抗の測定、接続箇所の確認、規格準拠のチェック |
非常用電源設備(自家発電機・UPSなど)
万一の停電時においても重要な機器を作動させ続けるために欠かせないのが非常用電源設備です。防災センター、医療施設、データセンター、サーバールームなどでは必須のシステムです。
非常用発電機の点検では、始動状況、燃料タンクの残量、冷却水および潤滑油漏れの有無、排気の状態などを確認します。また、無停電電源装置(UPS)の点検では、バッテリーの劣化状況、充放電機能、内部温度、警報履歴の確認が必要です。
点検のタイミングとしては、月次・年次といった定期的なスケジュールを基に、負荷運転試験を行って実際の稼働時と同様の条件での性能確認が求められます。
| 機器名 | 種類 | 点検内容 |
|---|---|---|
| 自家発電機 | ディーゼル発電機など | 燃料・冷却系統の確認、始動時間、漏れ点検、排気チェック |
| UPS装置 | バッテリー式・常時インバータ式など | バッテリー残量、警報表示の確認、端子の腐食有無、通電テスト |
このように、電気設備点検では各設備の機能と役割を正しく理解し、適切なタイミングと方法で点検を行うことが重要です。特に建物の使用目的や設置環境に応じて求められる安全基準や点検内容が異なるため、専門的な知識と豊富な経験を持つ技術者の関与が求められます。
電気設備点検の頻度とスケジュール管理

法定点検と自主点検の周期
電気設備点検には、法令で義務付けられた「法定点検」と、建物所有者や管理者が独自の判断で行う「自主点検」の2つの種類があります。これらは点検の目的や実施頻度が異なり、誤った理解や過少実施は義務違反や事故のリスクを高める原因となります。
| 点検の種類 | 根拠法令 | 実施者 | 主な対象施設 | 点検周期 |
|---|---|---|---|---|
| 法定点検 | 電気事業法 労働安全衛生法 | 電気主任技術者 | 高圧受電設備 自家用電気工作物 | 6ヶ月〜1年ごと |
| 自主点検 | 事業者の管理規程 各種ガイドライン | 社内の電気管理者 外部委託業者 | 全ての構内電気設備 | 月1回〜年1回(任意) |
法定点検は自家用電気工作物を所有・使用する者に義務付けられた点検であり、高圧受電設備を有するビル・工場・病院・学校などが対象となります。一方で、自主点検は日常的な安全確保やトラブル防止のために行われるもので、法的拘束力こそありませんが、継続的な設備の健全性を保つ上では欠かせません。
点検スケジュールの立て方と管理方法
効率的な電気設備点検を行うためには、年間を通じたスケジュール管理が重要です。特に法定点検は「次回点検予定日」を法的に明示することが求められるため、漏れのない計画が必須となります。
点検スケジュールの策定においては、以下のようなポイントが考慮されます。
- 法による定期点検周期(半年・年1回等)の遵守
- 設備ごとの劣化度や使用状況に応じた優先順位付け
- 建物の休業日・夜間利用などとのスケジュール調整
- 必要な予備部品や業者の調達時期への配慮
さらに、近年は点検履歴やスケジュールを一元管理できるソフトウェアやクラウドサービスの導入が増えており、アラート機能や進捗管理ができることで、ヒューマンエラーの低減と事務負担の軽減に寄与しています。
スケジュール作成の実例
| 月 | 点検内容 | 関係設備 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 法定年次点検(高圧受電設備) | 受変電設備 | 電気主任技術者 |
| 6月 | 避雷設備の動作確認 | 避雷導体・接地抵抗 | 自主点検員 |
| 10月 | 非常用発電機の始動試験 | 自家発電設備 | 業者委託 |
| 12月 | コンセントの絶縁測定 | 低圧配線・分電盤 | 社内技術者 |
建物規模や用途による点検頻度の違い
電気設備の点検頻度は、すべての建物で一律というわけではなく、建物の規模・用途・使用状況に応じて最適な点検間隔を調整する必要があります。これは誤った一律運用が、無駄のある管理や重大な点検漏れにつながるためです。
たとえば、大型商業施設やデータセンターのように常に高負荷がかかる建物では、発熱や老朽化リスクが高くなるため、法定点検に加え、月次・週次点検が推奨されます。一方、使用頻度が低い公共施設や倉庫等では、年1回〜2回程度の点検で対応可能な場合もあります。
| 建物種別 | 推奨点検頻度 | 主な留意点 |
|---|---|---|
| 病院・福祉施設 | 月1回以上(重要設備は週次) | 非常用電源・停電対策の重点確認 |
| 工場・製造施設 | 法定年2回+自主的な月次点検 | 高電圧機器や可動部の接触・摩耗点検 |
| オフィスビル(自家用受電) | 年1〜2回+定期目視点検 | 空調負荷・照明設備の劣化監視 |
| 商業施設・大型店舗 | 月次以上(法定+自主点検) | 昼夜利用に伴う設備劣化・損傷の確認 |
このように、点検周期の設定にあたっては建物用途ごとの電力消費傾向や利用の特性、トラブル発生例に基づいた経験値を加味しながら、定期的な見直しを行っていくことが、信頼性の高い電気設備運用の鍵となります。
電気設備点検のチェックポイント一覧

目視点検で確認すべき項目
電気設備点検の第一歩として、視覚により異常を察知する目視点検は不可欠です。目視点検により、設備外観の経年劣化や不具合を早期に発見できます。以下は主な確認項目です。
| 設備名 | 点検項目 | 異常の兆候 |
|---|---|---|
| 配電盤・分電盤 | 腐食、変色、配線の緩み | サビ、焦げ跡、異常な音や臭い |
| ケーブル類 | 断線、被覆の破れ | 外皮の亀裂、膨らみ、露出した導体 |
| 照明器具・スイッチ | 破損、緩み、動作確認 | スイッチの不動作、ちらつき、割れ |
| 絶縁体・碍子類 | ひび割れ、汚れ、破片の落下 | 汚損、碍子の欠けや破損 |
これらの項目はすべて感電や火災につながる重大事故の予防に直結するため、定期的な実施が必要です。点検時にはチェックリストを用いて、漏れや見落としを防ぎます。
測定点検の基本項目と使用機器
測定点検では、電気設備の性能や安全性を数値で評価します。主に以下の測定が行われ、いずれも専門の測定機器が必要となります。
| 測定項目 | 目的 | 使用機器 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗測定 | 漏電防止・絶縁劣化の確認 | 絶縁抵抗計(メガー) |
| 接地抵抗測定 | 落雷・漏電時の電流逃がし確認 | 接地抵抗計 |
| 電圧・電流測定 | 過負荷や電源トラブルの確認 | クランプメーター、テスター |
| 漏洩電流測定 | 不具合予兆の把握 | 漏洩電流計 |
| 温度測定 | 異常発熱検知 | 放射温度計、サーモグラフィ |
特にビルや工場などの大型施設では、温度異常や漏電トラブルは重大な設備事故を引き起こすリスクとなるため、定量的な評価が重要になります。測定には有資格者(電気工事士や電気主任技術者など)の立会いが推奨されます。
帳票作成と過去データの活用
点検結果をただ記録するだけでなく、帳票の管理と過去データの分析によって、蓄積的な保守が可能になります。以下は帳票作成時の基本的なポイントです。
- 日付・点検者の氏名・所属の明記
- 点検場所と設備番号の一元化管理
- 点検結果に基づく「改善提案」や「不具合報告」の記載
- 警告レベルや経過観察対象設備の明示
点検帳票は手書きの書式だけではなく、エクセルシートや点検アプリなどのデジタルツールの活用も進んでいます。これにより、次回点検までの履歴管理や傾向分析が効率化されます。
また、過去データとの比較やトレンド分析を行うことで、不具合の予兆を察知し、設備の寿命延伸やコスト削減に寄与します。特に異常振る舞いが徐々に現れるタイプのトラブル(接触不良、断線の進行など)では、この手法が非常に有効です。
安全対策と点検時の留意事項

感電防止と停電処置の方法
電気設備点検において最優先となるのが、作業員の感電防止と点検中の安全な停電処置です。感電事故は高所や狭小空間での作業中にも発生しやすいため、作業前に確実な電源遮断が必要です。
点検前には系統図をもとに点検対象設備の電源系統を明確にし、必要な遮断器・開閉器を操作して対象設備を完全に無電圧状態にする必要があります。誤って送電されないよう、作業中は「作業中・送電禁止」などのタグを取り付け、施錠・封印処置を実施するのが基本です。
また、高圧設備では充電部を活線で作業することは厳禁であり、必要に応じて接地棒の接続や絶縁養生なども適用すべきです。
点検員・作業者に必要な保護具と資格
電気設備点検を行う作業者は、法令で定められた保護具の着用と必要な資格の保持が求められます。作業内容や設備の電圧に応じ、一般的に必要とされる保護具は以下の通りです。
| 種類 | 用途 | 対応電圧 |
|---|---|---|
| 絶縁手袋 | 充電部への接触防止 | 高圧・低圧 |
| 絶縁靴 | 接地経路を断つことで感電リスクを低減 | 高圧・低圧 |
| ヘルメット(電気用) | 落下物対策と通電部接触時の保護 | 全設備共通 |
| 防護服 | アーク災害や火花から身体を保護 | 高圧 |
必要な資格は、電気工事士(第一種・第二種) や 電気主任技術者(第一種〜第三種) が代表例です。これに加えて、特別教育(低圧電気取扱業務)や技能講習(高圧・特別高圧)を受講していることも、実務上の要件として重要です。
作業前の安全確認手順とリスクアセスメント
電気設備点検の安全対策では、事前の安全確認手順を徹底するとともに、リスクアセスメントの実施が不可欠です。作業現場や設備に応じて想定されるリスクを一覧化し、対策を講じたうえで作業に入る必要があります。
作業前に実施すべき主な確認事項
| 確認項目 | 目的 |
|---|---|
| 点検対象設備の系統・回路の確認 | 誤操作・誤送電の防止 |
| 遮断器・断路器の操作状況 | 無電圧状態の確認 |
| 接地の有無確認と追加接地 | 静電誘導・残留電圧の除去 |
| 保護具・測定器の点検 | 機能不良による安全性低下の防止 |
| 作業体制の確認(班分け・責任者明確化) | 連携不良や指示ミスの回避 |
リスクアセスメントでは、危険源(高電圧、湿潤環境、可燃性ガスなど)を洗い出し、それぞれの発生頻度と結果の重大性を評価します。この結果に基づき、必要な対策(遮断、隔離、養生、機器変更等)を講じ、リスクレベルを許容範囲まで引き下げることが重要です。
また、作業ごとに作業指示書やKY(危険予知)活動シートを実施することで、小さなリスクや見落としがちな要因も体系的に管理できます。
点検業務を効率化するためのツールと外部委託

点検アプリやチェックリストの活用
近年、電気設備点検業務の現場でデジタル化を通じた効率化が進んでおり、点検アプリや電子チェックリストの導入が増えています。特にタブレットやスマートフォンで使用できる点検支援アプリは、現地での記録作業を簡略化し、リアルタイムでのデータ共有も可能にします。
代表的な点検アプリには「保安点検PRO」や「点検ヘルパー」などがあり、これらは点検項目のテンプレート化、異常値の自動判定、写真の添付機能などを備え、手作業による記録ミスや漏れを防ぎます。また、帳票作成機能も充実しており、PDFやExcel形式での出力が可能なため、報告書の作成時間も大幅に短縮されます。
さらに、チェックリストのデジタル化により、複数年分の履歴を一括で管理できるようになり、過去のトラブル傾向の分析を可能にします。これにより、次回点検時の注意点を事前に把握することも容易になります。
外部業者へ委託するメリットと選び方
電気設備点検を外部の専門業者に委託することは、業務効率の向上と法令遵守の面からも大きなメリットがあります。第一に、外部業者は電気主任技術者などの有資格者を常駐させており、高い専門性と経験値に裏打ちされた点検を実施できます。
また、年間契約による定期点検のスケジュール管理や緊急時の対応など、一貫した保守体制を構築できる点も魅力です。特に、法定点検項目を正確に把握した上で点検を行えるため、電気事業法や労働安全衛生法に基づいた報告義務へも対応可能です。
外部業者選定時には、以下のような比較表を参考とするとよいでしょう。
| 選定基準 | 確認ポイント | 重要度 |
|---|---|---|
| 保有資格 | 電気主任技術者(第三種以上)、電気工事士など有資格者が在籍しているか | 高 |
| 実績と信頼性 | 同業他社・同規模施設での点検実績の有無 | 中 |
| 点検内容の明確さ | 契約前に点検項目・方法・使用機器の説明があるか | 高 |
| 緊急対応体制 | 異常発生時の即時対応可否 | 高 |
| 料金体系 | 初期費用・年間契約費用・オプション費などの透明性 | 中 |
さらに、事前に現地調査を実施してくれる業者かどうかも重要です。現地確認を行わずに見積もりを出すケースでは、契約後に追加費用が発生するリスクがあります。契約内容を事前に書面で明確化しておくことも、トラブル防止につながります。
代表的な点検業者と料金相場
点検業務を委託する場合、業者ごとに料金体系やサービス内容が異なるため、数社から相見積もりを取ることが基本です。以下に代表的な電気設備点検業者とその特徴、料金の目安を示します。
| 業者名 | 主な対応エリア | 主なサービス内容 | 年間点検費用(目安) |
|---|---|---|---|
| 関電工 | 関東圏 | 受変電設備点検、高圧機器点検、24時間緊急対応 | 30万円~100万円(設備規模により変動) |
| 日本電設工業 | 全国 | 電気保安管理業務全般、月次点検、年次点検 | 20万円~80万円 |
| 中部電気保安協会 | 中部地方 | 法定点検、事故調査、リスクアセスメント対応 | 25万円~90万円 |
| 東電パワーグリッド | 首都圏 | 商業施設・工場向けの高圧設備保守 | 35万円~120万円 |
料金相場は、建物の規模、保有設備の種類、点検の回数によって変動します。たとえば、高圧受変電設備を有する大型ビルでは年100万円以上の費用がかかることもあります。逆に、低圧設備しかない中小規模の事務所ビルでは月額1万円程度の契約で済むこともあります。
費用だけでなく、定期点検に加えてメンテナンス提案を行う業者を選ぶことで、予防保全型の施設運営が可能になります。点検の「異常発見」だけでなく、「異常の予兆を検知する」視点をもった業者とのパートナーシップが、安全性とコストの最適化につながると言えるでしょう。
電気設備点検に関係する法令と参考資料
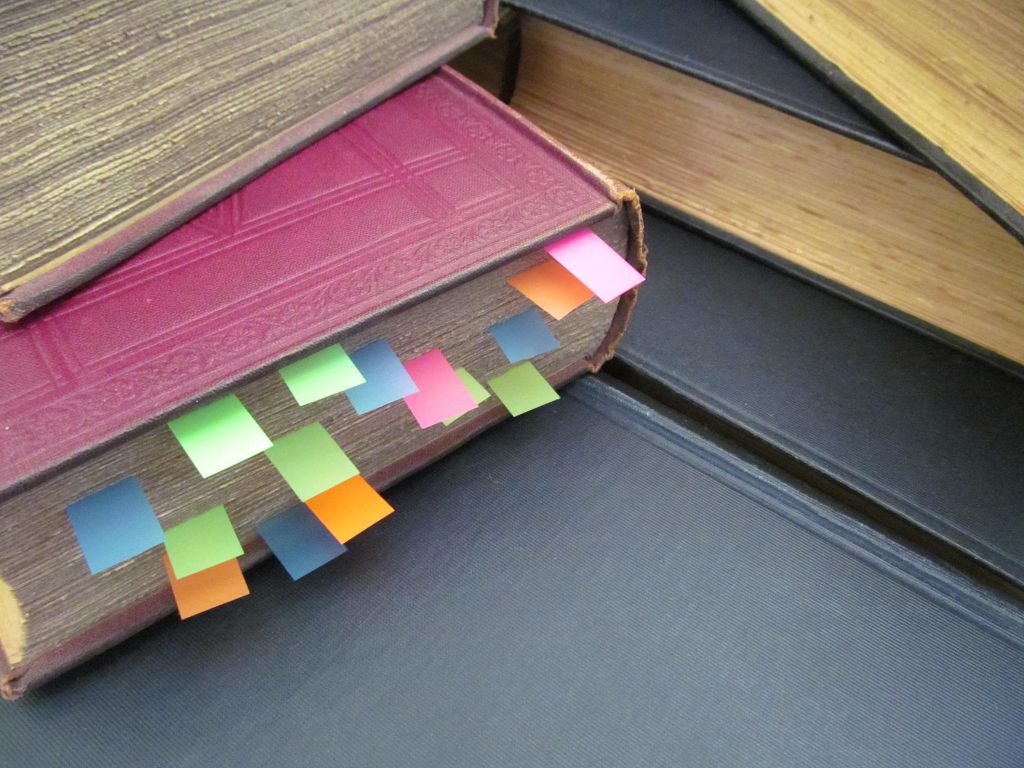
労働安全衛生法と電気事業法
電気設備点検を実施するにあたっては、「労働安全衛生法」や「電気事業法」などの法令を遵守することが必須です。これらの法律は、作業員の安全と設備の保全、さらには社会全体への影響を考慮しており、点検の実施周期や方法、安全対策などの指針を明確にしています。
労働安全衛生法は、作業における労働者の安全を確保することを目的としており、高圧電気設備や感電防止策に関する指針を含んでいます。特に、労働安全衛生規則第351条〜第361条には、電気に関する危険有害業務の管理方法や点検頻度が規定されています。
電気事業法では、事業用電気工作物に関する維持・管理や定期点検の義務が定められており、主任技術者の選任や保安規程の整備が求められます。定期的な外部検査(保安監督部による定期検査)も必要とされます。
| 対象法令 | 主な内容 | 関係者の義務 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 作業者の安全確保、感電防止、高所作業の安全性 | 安全教育の実施、定められた保護具の使用、安全作業手順の遵守 |
| 電気事業法 | 電気設備の保安確保、主任技術者の設置、保安規程の整備 | 事業者の届出義務、定期点検の実施、検査記録の保存 |
関連ガイドラインと標準点検マニュアル
法令に加えて、業界団体が策定するガイドラインや標準点検マニュアルも、電気設備点検の実施において重要な参考資料です。これらは現場での実務に即しており、最新の情報や実用的な手順が記載されています。
代表的な資料として、「一般財団法人日本電気協会」が作成する『電気設備技術基準とその解釈』、『発電所電気設備保安点検マニュアル』などがあります。これらには、機器ごとの詳細な点検方法や判断基準、必要な測定機器などがまとめられており、点検品質の均一化と作業の効率化に寄与します。
その他にも「電気設備の保守点検要領(国土交通省)」や「ビル電気設備の維持管理指針(建築設備技術者協会)」など、施設の種類や用途別に実務者向けの資料が存在します。
| 参考資料名 | 発行機関 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 電気設備技術基準とその解釈 | 日本電気協会 | 電気工作物に対する技術的基準と具体例 |
| 発電所電気設備保安点検マニュアル | 日本電気協会 | 発電所設備における点検方法と基準 |
| 電気設備の保守点検要領 | 国土交通省 | 官公庁施設等の電気設備の点検要領 |
| ビル電気設備の維持管理指針 | 建築設備技術者協会 | ビルメンテナンスにおける電気管理基準 |
参考になる学会・団体(電気技術者協会など)
電気設備点検をより深く理解し、制度の最新動向や技術革新に対応するためには、専門団体や学会から発行される情報を継続的に収集することが重要です。こうした団体は、技術セミナーや講習、専門誌の発行、指導資料の配布を通して実務者の支援を行っています。
主要な関連団体には以下のようなものがあります。
- 一般社団法人 電気技術者協会:主任技術者を中心とした全国的な組織で、技術情報誌『月刊 電気と工事』や「保安講習会」などを通して、保安業務の品質向上を図っています。
- 一般社団法人 日本電気協会:電気事業分野における統一的な基準や技術的ガイドラインの整備を行い、電気安全の向上を目的としています。
- 公益社団法人 日本電気技術者センター:電気主任技術者試験の支援、免状更新制度、教育・研修プログラムの提供を行っています。
これら団体の提供する教育プログラムや公開資料を活用することで、法令や技術の変化に対応した点検活動が可能となり、組織的な保安力の向上にもつながります。
まとめ

電気設備点検は法令遵守と安全確保の両面から極めて重要です。受変電設備や避雷設備などの点検は、感電や火災のリスクを防ぐために不可欠です。定期的な自主点検と法定点検を計画的に実施し、チェックリストや外部委託を活用することで業務の効率化が図れます。電気事業法や労働安全衛生法を遵守し、日本電気技術者協会などの資料を参考にしながら、安全で確実な点検を行いましょう。